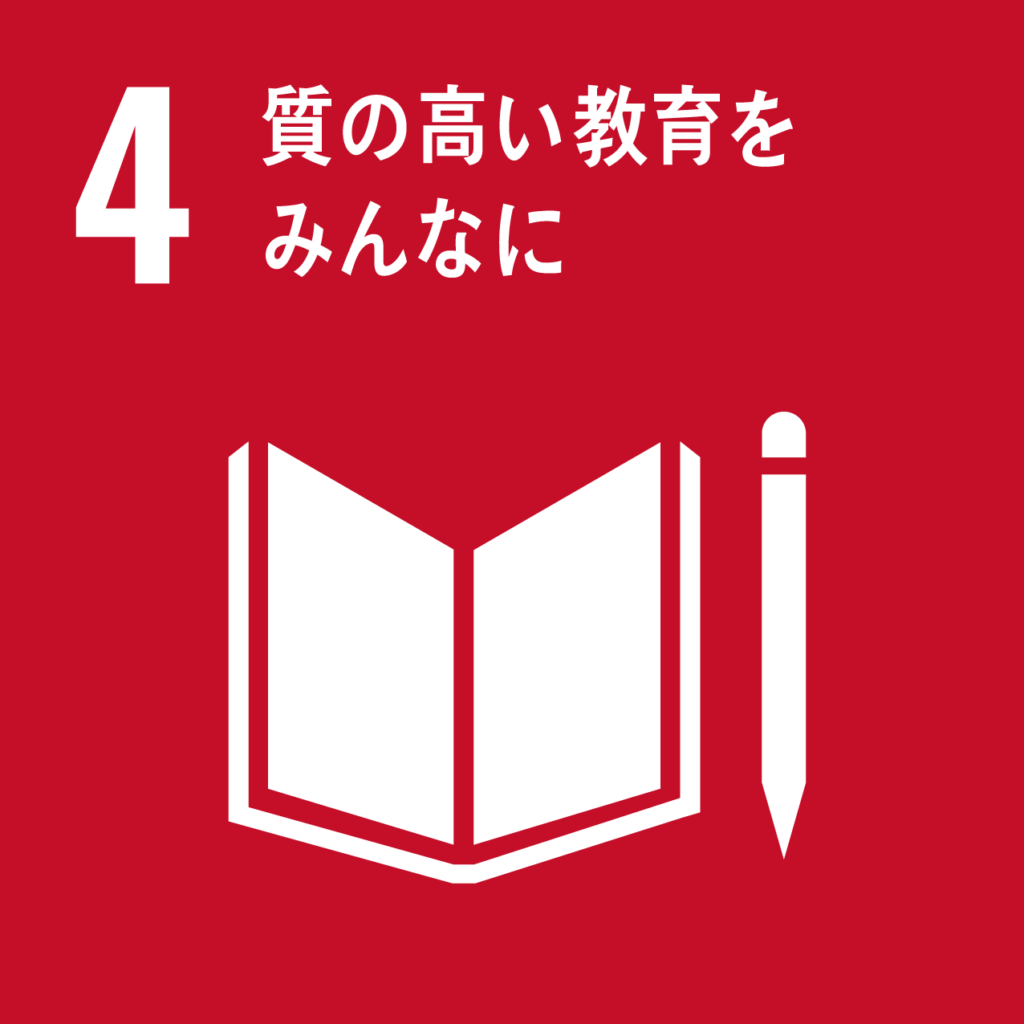
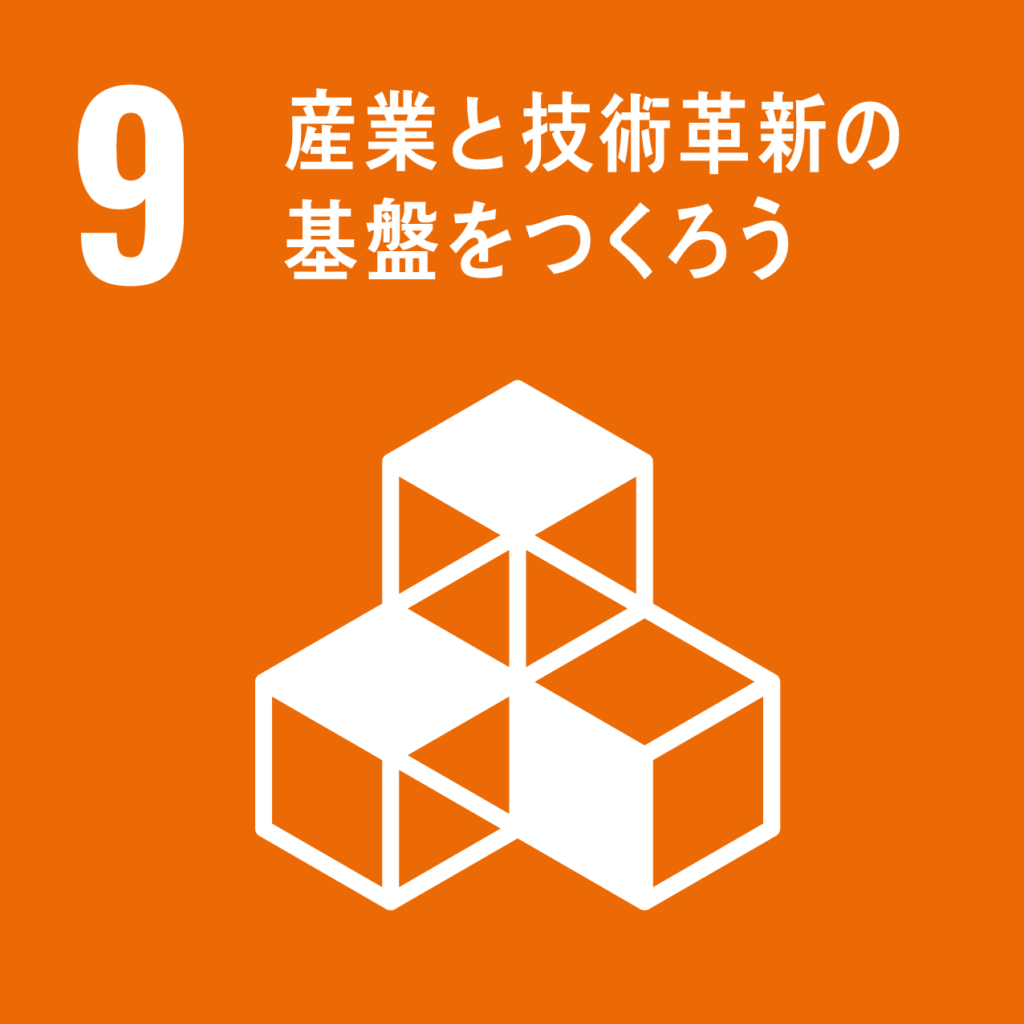
「梅澤朗広の採用SDGs」第19回目は、「NotebookLMで始める!社員教育をAIで仕組み化する3ステップ」です。
先日、あるクライアントから「自社のホームページにチャットボットを導入したい」と相談を受けました。そこで仲間のAI事業者に繋いだところ、月額1万円ほどのチャットボットとNotebookLMを組み合わせ、わずか数時間でお客様の質問に自動で答える仕組みを完成させてしまいました。
NotebookLMとは、Googleが提供する「自社専用の知識AI」を簡単に作れるアプリです。社内マニュアルや議事録、商品カタログなどのPDFやドキュメントをアップロードすると、AIが内容を理解し、質問に自然に答えてくれる“社内版ChatGPT”のような存在です。専門知識を持つ社員がそばにいる感覚で、必要な情報をすぐに引き出せるのが特徴です。
つまり、社員が「この手順書はどこ?」「取引先A社の条件は?」と聞けば、NotebookLMが瞬時に答えてくれる。人に聞くより早く、しかもアップロードした情報から回答するので正確に、しかも24時間対応可能です。
このAI事業者に話を聞くと、「NotebookLMは社内教育にも活用できる」とのこと。そこで今回は、“すぐに試せるAI活用術”として、その具体的な使い方をご紹介します。
目次 ➖
採用“後”こそ、企業の真価が問われる時代へ
採用定着士の高木先生の記事「#8 社員の定着は“未来の見える化”から!キャリアパスで育てる仕組み」
(https://tama-work.jp/news/https-tama-work-jp-news-takagi-saiyouteicyakushi-18/)
では、「せっかく中途採用した社員が半年や1年で辞めてしまう」という悩みを紹介していました。
理由を聞くと、「自分のキャリアが見えない」「この先成長できる気がしない」といった声が多いそうです。
こうした課題に加え、企業では次のような声もよく聞かれます。
- 採用してもすぐに辞めてしまう
- 教える時間が足りない
- 教える人がいない、やり方が人によってバラバラ
特に中小企業では、現場が忙しく、ベテラン社員は自分の仕事で手一杯。マニュアルの更新も追いつかず、“教え方”も“覚え方”も人に依存してしまうのが現状です。

今、求められているのは、“人の善意や根性”に頼らない仕組みづくりです。AIをうまく使えば、採用後の教育・定着・業務効率化を同時に進めることができます。高木先生も指摘するように、社員が定着するかどうかを決めるのは、入社後のコミュニケーションの設計と、さらに「誰でも迷わずできる仕組み」=マニュアルの存在です。
AIを“第二の教育担当”として活用し、現場で自然に回る学習環境を作ることが大切です。
現状分析―中小企業が抱える“教育の非効率”とは?
中小企業では、次のような「教育のムダ」がよく起きています。
- ベテランの時間が奪われる:新人の質問対応で作業が何度も中断する
- やり方が人によってバラバラ:口で伝えるだけのOJT(現場教育)では品質が安定しない
- マニュアルが古い、または存在しない:実際の現場とのズレが広がる
- 同じ質問が何度も発生し、生産性が下がる
たとえば、
「教えたつもりでも現場では別のやり方をしている」「忙しい時期に新人が来て、教育が後回しになる」「大事なポイントが資料に散らばっていて見つけにくい」などです。

こうした非効率は、最終的に早期離職やクレームの増加、やり直しコストとして跳ね返ってきます。つまり、根本的な原因は「共通のやり方」がない、あるいは更新されていないことにあります。
これからの時代は、この“共通のやり方の不在”を解消することが大切です。そのために役立つのが、AIとマニュアルを組み合わせた仕組みづくりです。AIをうまく活用すれば、誰でも同じ品質で学べる環境を整えることができます。
次の章では、その具体的な方法――AIを「第二の教育担当」にする仕組み――を紹介します。
解決策の方向性―AIを“第二の教育担当”に育てよう
OJT(職場での実践教育)の限界を超えるカギは、「誰が教えても同じ品質で学べる仕組み」を作ることです。
ここで有効なのが、AIを使った業務マニュアルの自動化です。
Googleが提供する「NotebookLM」というAIツールは、社内資料(手順書や企画書・よくある質問など)を読み込み、目的別に要約・整理し、質問にも答えてくれます。
この仕組みを導入すると、マニュアル作成にかかる時間を大幅に減らせるだけでなく、改訂も簡単になり、「誰かにしかできない仕事(属人化)」を防ぐことができます。さらに、新人が自分で学びやすくなるため、教育のスピードが上がります。
AIは人間の代わりに教える存在ではなく、育成を支えるパートナーです。
現場の知恵を一つにまとめ、見える形にすることで、誰でも迷わず作業できる“共通のやり方”を作ることができます。
結果として、社員の理解度やモチベーションが上がり、早く一人前になれることや、離職防止効果につながります。
導入事例・イメージ紹介―現場が変わる、定着が進む
・製造業での作業標準書の統合と最適化
複数の工場で異なるフォーマットの作業標準書が使用されており、統一性に欠けていました。NotebookLMに既存の作業標準書をすべてアップロードし、「これらの資料を統合した標準的な作業マニュアルを作成してください」と指示したところ、共通のフォーマットと手順を持つ統一マニュアルが生成されました。
・飲食店での調理マニュアルの多言語化
外国人スタッフを雇用している店舗では、調理マニュアルの多言語化が課題でした。NotebookLMに日本語の調理マニュアルをアップロードし、「このマニュアルを英語/中国語/ベトナム語に翻訳してください」と指示しました。AIは単なる翻訳だけでなく、各国の文化的背景も考慮した自然な表現で多言語マニュアルを生成。「各国の食文化に合わせた説明を追加してください」という追加指示により、より理解しやすい内容に調整することができました。この取り組みにより、外国人スタッフの研修期間が平均2週間短縮され、調理品質の均一化にも成功しています。
・不動産会社での物件説明マニュアルの自動生成
物件ごとに説明マニュアルを作成する作業に多くの時間を費やしていました。NotebookLMに物件データ、周辺環境情報、過去の成約事例などをアップロードし、「これらの資料を基に、〇〇物件の説明マニュアルを作成してください」と指示しました。
AIは物件の特徴や周辺環境を分析し、セールスポイントを効果的に伝えるマニュアルを生成。「ターゲット層別の訴求ポイントを追加してください」という追加指示により、顧客層に合わせた提案ができる内容に仕上げることができました。この取り組みにより、マニュアル作成時間が従来の25%程度に短縮され、成約率も10%向上したという成果が報告されています。
事例の共通点は、「小さく始めて運用で育てる」ことです。
では、明日から何をすればよいか。3つのステップで現場に落とし込みましょう。
今日から動く:3ステップで“教える時間”を半減へ
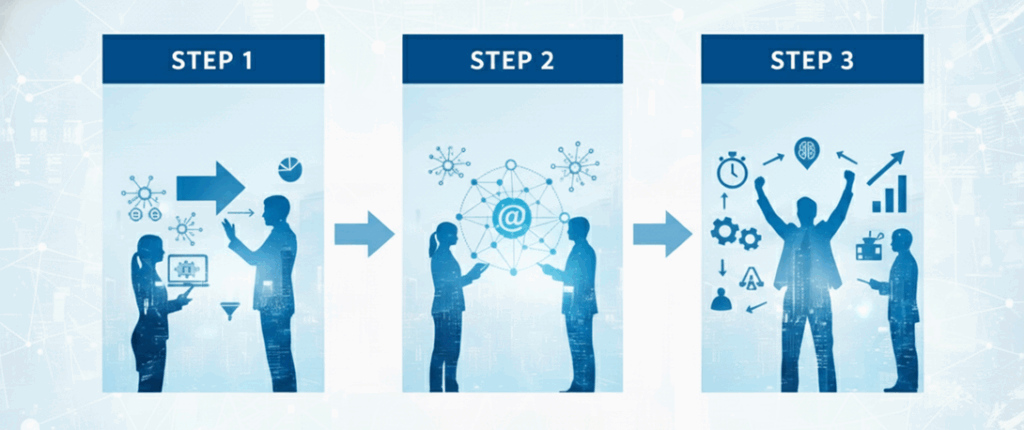
Step1:現場の“よくある質問”をリスト化する
まず、過去1か月の質問やミスを振り返ります。
「誰が・いつ・どこで・なぜ詰まったか」を短くまとめ、頻度の高い順に並べましょう。
これがAIが学ぶための“教科書”になります。
Step2:社内文書をNotebookLMに読み込ませて整理する
既存の手順書・チェックリスト・企画書などをAIに読み込ませます。そして、「初心者向け」「安全重視」「リーダー向け」など目的別にまとめます。見出しや注意点、確認方法(OK・NGの例)を明記することで、誰でも迷わず行動できます。
Step3:運用する
現場で“調べる→試す→直す”の流れを回します。質問があればAIが自動で答え、申請や報告テンプレートも呼び出せるようにします。チャット上で完結するので、作業を止めずに教育が進みます。
NotebookLMを活用した初心者向けの実装手順
1)準備:最新の資料だけを集め、古いものは削除。
2)アップロード:テーマ別にノートを分ける(例:安全・品質・設備・事務)。
3)生成:新人向けに300字程度で要約し、専門用語に注釈を加える。
4)展開:共有リンクを展開し、現場でいつでも見られるようにする。
5)更新:月に一度、最新の内容に保つ。
今後の展望とまとめ―AI時代の“人を活かす”採用戦略へ
社員がしっかり定着している企業は、生産性や品質も安定しやすくなります。AIは人を置き換えるものではありません。現場の知識を整理して共有することで、リーダーの負担を減らし、人がより「考えること」「伝えること」に集中できる環境をつくります。
採用のゴールは「入社」ではなく「定着と成長」です。
AIを上手に活用すれば、
- 教える時間を減らせる
- 自分で学ぶ社員が育つ
- 結果として離職が減る
―この3つを同時に実現できます。
育成を“事業成長のチャンス”に変えるなら、まずは最重要テーマ1つでAI×マニュアルを始めてみましょう!
プロフィール
梅澤 朗広
SDGusサポーターズ株式会社 代表取締役
日本JC公認SDGsアンバサダー
FC NossA八王子 アドバイザリーボード
大切にしている価値観:感謝・貢献・共創
野村證券、東京ヴェルディを経て2019年にSDGusサポーターズ株式会社を設立。SDGsの「持続可能な社会の実現」「誰一人とりのこさない」の理念に共感し、企業に対してCSV(共通価値の創造)の観点で事業活動と社会活動の両立に向けた経営サポートをおこなっています。SDGsと自社の活動に対する理解を深めてアクションを考えるワークショップや、様々なパートナーと連携して営業・広報・採用のサポートをおこなっています。
SDGsについて興味を持っている・相談したいなど、ぜひコチラにお気軽にお問合せください。


