

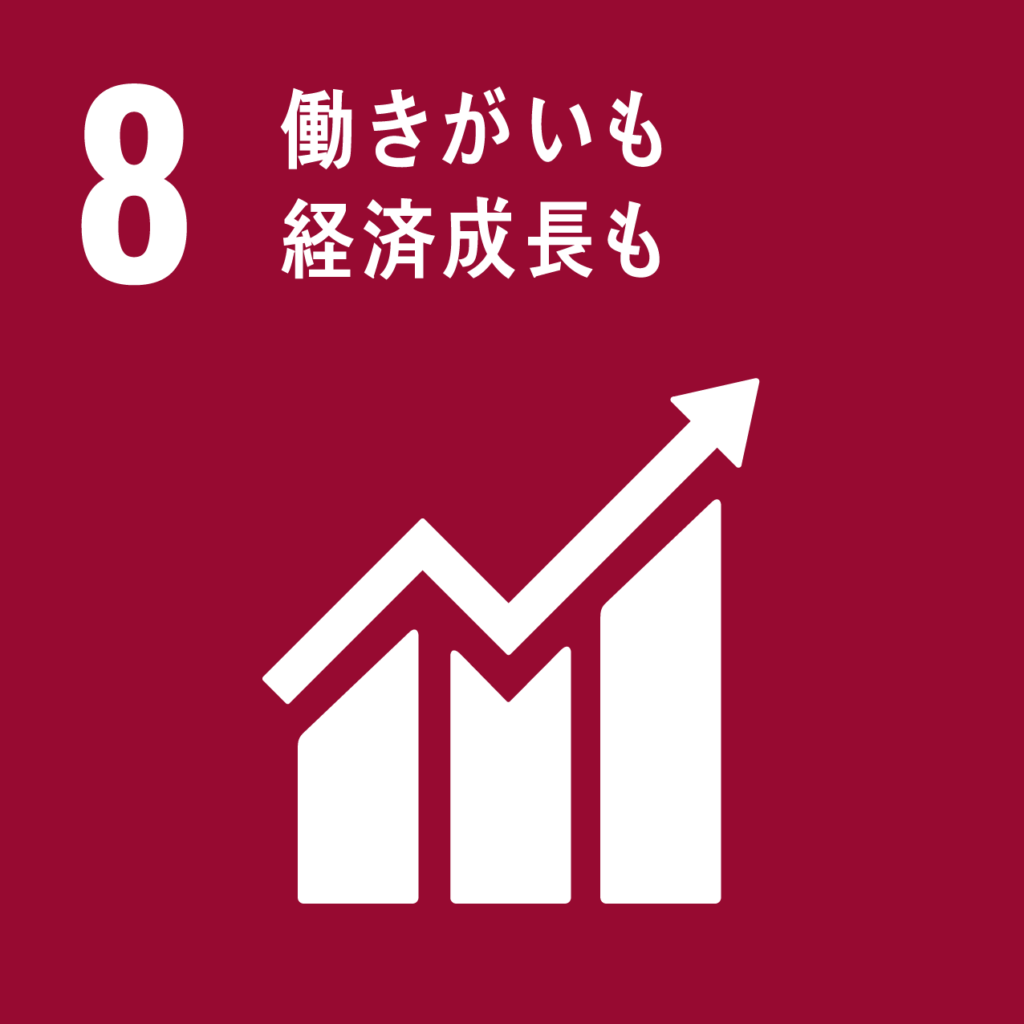
最近、中小企業でも「社員の健康を守ること」が大きな経営課題になっています。たとえば、ストレスや長時間労働で体や心を壊してしまい、1か月以上休む人が出るケースがあります。
さらに、病気や不調まではいかなくても「なんとなく体調が悪いまま働く」状態が、会社にとって大きな損失になります。これは欠勤よりも目に見えにくいのですが、1人あたり年間100万円以上の損失になることもあるといわれています。少人数で業務を回している中小企業にとっては、一人が倒れると業務全体に影響がより出やすくなります。
だからこそ、社員が元気に働けるように健康経営に取り組むことは、利益を守り、会社を続けていくために欠かせない対策になっています。今回は「健康経営」がなぜ今、企業にとって重要なのか、その実践方法や導入を後押しする制度・サービスを紹介します。
目次 ➖
健康経営がもたらすメリットとは?
「健康経営」とは、社員の健康を守ることを経営課題と位置づけ、会社の成長につなげる取り組みです。これを導入するとどんなメリットがあるのでしょうか。
■社内へのメリット
1. 離職率の低下 働きやすい環境が整うことで、社員が長く定着する
2. 生産性の向上 心身が健康であれば集中力が高まり、成果が上がる
3. 事故や病欠の減少 体調不良による欠勤が減り、業務の停滞を防ぐ
4. 職場の活気 コミュニケーションが活発になり、働く雰囲気が明るくなる
■社外へのメリット
1. 採用力の向上 「健康に働ける会社」という評価は、応募者にとって大きな魅力になる
2. 金融・保険の優遇 銀行の金利優遇や保険料の割引など、外部からの信頼が増す
3. 企業ブランドの強化 社員を大切にする姿勢は、取引先や地域社会からの信頼につながる
国も健康経営を強く推進しており、今や「やっておけば良いこと」ではなく、中小企業が生き残るための必須戦略といえるのです。
「健康経営優良法人」という信頼の証
健康経営を実践していることを対外的に示す方法として注目されているのが「健康経営優良法人」の認定制度です。これは経済産業省などが進める仕組みで、中小企業を含む多数の法人が参加しています。認定企業数は年々増加しており、令和7年度(2025年度)には大規模法人部門で3,400法人、中小規模法人部門で19,796法人が認定されました。
認定までの流れ
1. 健康に関する方針や目標を表明する
2. 健康診断・アンケート等で現状を把握し、改善目標を設定する
3. 社員の健康診断体制の整備や運動習慣の促進など具体的な施策を実行する
4. 実施した取組みを評価し、改善を繰り返す(PDCAサイクル)
認定を受けることにより、企業は「社員の健康を重視している法人である」ということを対外的に示すことができ、企業ブランドの強化やさまざまな優遇制度の活用に役立てることが可能です。

過去最多1,000件超の労災認定が示す、中小企業に必要なサポートとは?
健康経営の必要性は理解していても、中小企業が自力で進めるのは簡単ではありません。たとえば、精神障害による労災の支給決定件数は、2024年度に1,055件となり、過去最多・初めて1,000件を超えました。心身の不調は誰にでも起こり得るリスクを考えると、専門スタッフが少ない中小企業にとって、健康診断後のフォローやメンタルケアを社内だけで完結するのは負荷がかかってしまいます。
そこで有効なのが、保険会社が提供する「健康経営支援サービス」です。保険契約とセットで健康相談や生活習慣改善プログラムを活用でき、費用を抑えつつ外部の専門力を借りられるため、限られたリソースで健康経営を継続する実践的な手段となります。
健康経営を支える保険サービスの比較
保険会社も「健康経営」を後押しするための独自サービスを提供しています。ここでは代表的なサービスを紹介し、それぞれの特徴と活用シーンを整理しました。
アクサ生命:「健康経営アクサ式」
全国に配置された「健康経営アドバイザー・エキスパートアドバイザー」が、従業員の健康診断結果やアンケートなどをもとに、働きやすい職場環境づくりや生活習慣改善、ストレスチェック支援などを実施。産業医プログラムなどの相談体制も用意されており、健康経営の取り組みを段階的に強化したい企業に適しています。
明治安田生命:「みんなの健活プロジェクト / 健活年齢サービス」
定期的な健康診断(“けんしん”)を通じて加入者の健康状態を可視化し、将来リスクを予測する「健活未来予測モデル」を活用しています。「ベストスタイル 健康キャッシュバック」等の商品では、健康診断結果に応じてキャッシュバックがあり、加入者の健康年齢差が改善するという統計データも報じられています。法人・個人両方の加入商品があり、診断結果の提出が条件のサービスが含まれています。
AIG損保:「健康経営サポートプラン」
死亡補償を省いた、ケガ・疾病の医療補償のみで加入できる新しい業務災害総合保険プランです。入院・医療費用補償を主契約とし、健康経営に関するコンサルティングや健康相談・チャットサービス・セカンドオピニオンなど外部専門機関との連携によるフォローアップ機能を備えています。小規模事業者にとっても補償と健康支援を両立しやすい設計といえます。
大同生命:「会社みんなでKENCO+」および「KENCO SUPPORT PROGRAM」
健康診断の受診促進、生活習慣病リスク分析、ストレスチェック機能、健康行動の見える化(歩数記録・ウェアラブル端末連携など)を含む「KENCO SUPPORT PROGRAM」がセットされた健康増進型保険です。歩数基準をクリアすれば翌年の保険料割引やポイント付与といったインセンティブもあり、予防と万一の保障を同時に求める企業に向いています。
第一生命:「団体保険付帯サービス / QOLism」
団体保険を契約する企業向けに、福利厚生+健康経営の支援が受けられるサービスを提供しています。「DL Benefit Premium」などを通じて、健康相談・心身の健康サポート・育児・介護などの日常のケアの優待利用が可能です。また、健康経営優良法人認定取得支援や、スマホアプリ「QOLism」を利用した生活習慣の記録・改善機能などを導入しており、社員の健康増進と従業員満足度向上を図る設計となっています。
健康経営は未来への投資

社員は会社にとって最も大切な「人財」です。健康経営を導入することで、採用力・定着率・生産性の向上だけでなく、金融・保険面での優遇や企業ブランド向上といったメリットも得られます。
多摩地域の中小企業にとって、健康経営は単なる福利厚生ではなく「生き残り戦略」です。小さな一歩から始めることが、未来の大きな成長につながります。 みなさんの会社も、今日から「社員の健康を守る経営」に取り組んでみませんか?
プロフィール
梅澤 朗広
SDGusサポーターズ株式会社 代表取締役
日本JC公認SDGsアンバサダー
FC NossA八王子 アドバイザリーボード
大切にしている価値観:感謝・貢献・共創
野村證券、東京ヴェルディを経て2019年にSDGusサポーターズ株式会社を設立。SDGsの「持続可能な社会の実現」「誰一人とりのこさない」の理念に共感し、企業に対してCSV(共通価値の創造)の観点で事業活動と社会活動の両立に向けた経営サポートをおこなっています。SDGsと自社の活動に対する理解を深めてアクションを考えるワークショップや、様々なパートナーと連携して営業・広報・採用のサポートをおこなっています。
SDGsについて興味を持っている・相談したいなど、ぜひコチラにお気軽にお問合せください。


