


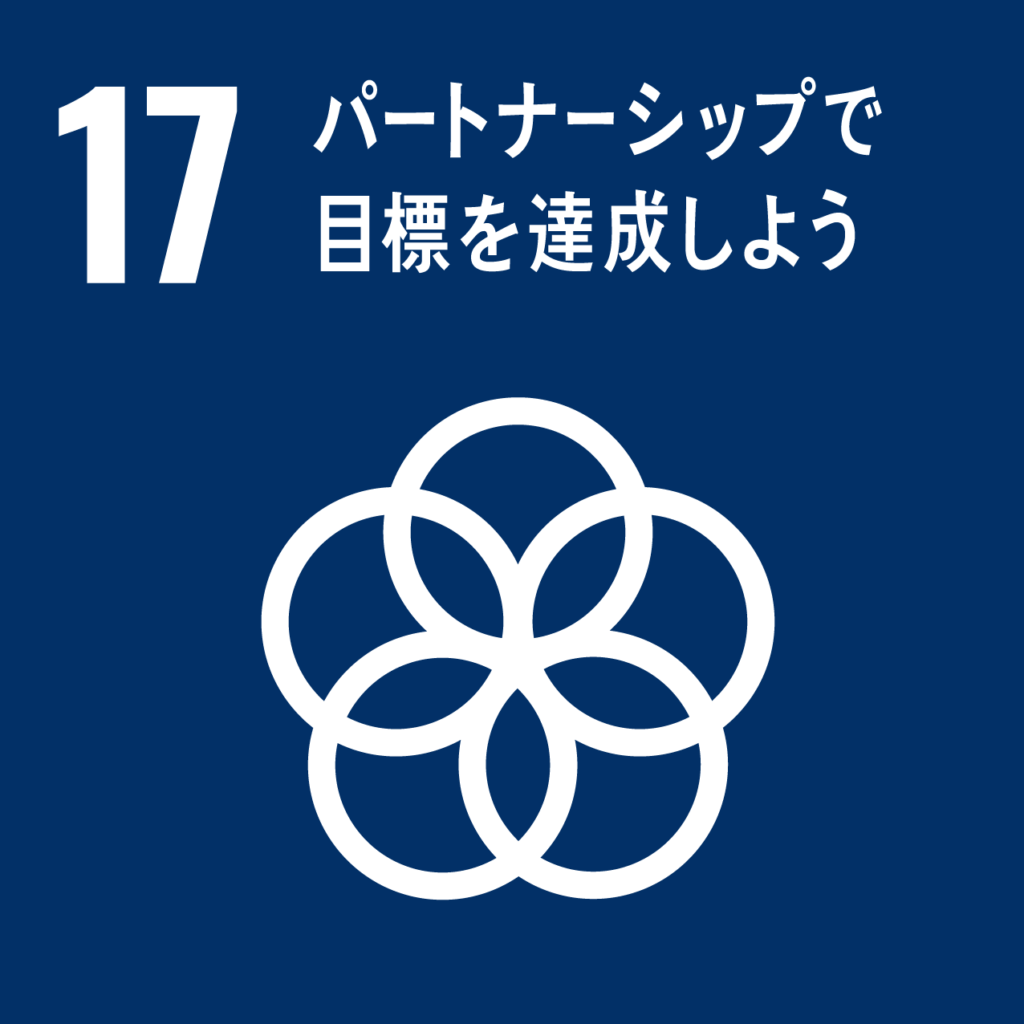
前回は、気候変動による災害リスクの増大が企業経営にも深刻な影響を与え始めている現状を踏まえ、いざという時に役立つBCP(事業継続計画)による備えについてご紹介しました。
今回は、その簡易版ともいえる「事業継続力強化計画」を取り上げます。BCPよりもシンプルな構成で、中小企業でも短期間で作成できるうえ、国による認定制度があり、認定を受けることで税制優遇や金融支援などのメリットが得られます。
事業継続力強化計画の概要から作り方、そして活用事例までご紹介していきます。
目次 ➖
国が認定する“中小企業の防災武器”
事業継続力強化計画は、中小企業庁が認定する防災・減災のための取り組み計画です。 自然災害、感染症、サイバー攻撃、取引先の倒産など、事業を止めかねないリスクをあらかじめ想定し、発生時でも事業を継続または早期復旧できるよう備えることを目的としています。
■認定を受けるメリット
認定を受けることで得られるメリットは、事業の信頼性や資金調達力を高め、さらには補助金や税制面でも優遇が受けられるなど、経営のあらゆる局面で効果を発揮します。具体的には次の4つが挙げられます。

1. 信頼性向上
経済産業省認定のロゴマークをHPや名刺に掲載でき、取引先や顧客からの安心感が増します。
2. 金融支援
日本政策金融公庫による低利融資や、信用保証協会での追加保証枠の設定などの金融支援が受けられます。
3. 補助金加点
ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金などで審査加点が得られます。
4. 税制優遇
防災・減災設備への投資に対し、即時償却や税額控除が適用されます。
認定までの4ステップ
こうしたメリットを最大限に活かすためには、まず認定を受けることが不可欠です。
「事業継続力強化計画」は、専門家だけでなく自社の経営陣や現場担当者が協力すれば、比較的短期間で作成できます。
作業は大きく4つのステップに分けられ、手順を踏めば初めての企業でも無理なく取り組めます。
ステップ1:自社のリスク洗い出し
水害、停電、感染症、仕入先の被災など、業務が止まる原因を具体的に挙げます。
→ 現場責任者やベテラン社員を交えることで、経営者だけでは見落とす現場リスクも把握できます。
ステップ2:対策の具体化
* 代替仕入先の確保
* 非常用発電機の導入
* 社員安否確認アプリの導入
* 在宅勤務環境の整備
ステップ3:申請書の作成
自社単独で計画を申請する場合は、電子申請で手続きを行います。申請は「事業継続力強化計画・電子申請システム( https://www.keizokuryoku.go.jp/ )」から可能です。ただし、この申請には「GビズIDアカウント」が必要となります(gBizIDプライムまたはgBizIDメンバー)。アカウントの取得にはおよそ2週間ほどかかるため、余裕をもって早めに準備しておくことが大切です。
ステップ4:認定書の交付
申請から認定までおおよそ1〜2か月。認定後は年1回の見直しを行うと効果的です。
事例で見る!有事に強い会社の備え

競合と手を取り合い、地域の移動を守る ― 赤碕ダイハツ有限会社の挑戦
赤碕ダイハツ有限会社は、地域の移動手段を守るため、競合他社と連携して「琴浦モビリティグループ」を結成しました。災害時には部品や車両の共同確保、社員の相互応援、輸送ルートの確認などを実施し、修理や緊急移動サービスを継続可能にしています。この取り組みは、地域全体でリスクに備えるモデルケースであり、運送業や小売業にも応用できます。
◆取り組みの詳細はこちら
https://kyoujinnka.smrj.go.jp/case/58/
リスクを「自分事」に変える ― 株式会社ハートコンピューターの事業継続力強化
株式会社ハートコンピューターは、事業継続力強化計画を経営リスクの洗い出しと従業員の意識改革の機会としました。地震や水害、感染症、サーバーダウンなど多様なリスクを想定し、影響を徹底分析。これにより従業員一人ひとりが「もしも」を自分事として捉えるようになりました。計画には行動マニュアルやリモート環境、データバックアップ体制を盛り込み、災害時でも冷静な対応を可能にしています。この事例は災害対策にとどまらず、平時の経営改善や危機意識の向上にも役立つ点を示しています。
◆取り組みの詳細はこちら
https://kyoujinnka.smrj.go.jp/case/57/
サプライチェーン全体で備える ― 株式会社丸信の安定供給体制づくり
株式会社丸信は、供給停止が顧客に大きな影響を及ぼすリスクに備え、事業継続力強化計画を活用しました。同社は自社だけでなく主要仕入先や協力会社とも計画を共有し、災害時には代替供給元や生産拠点を確保できる体制を整備。その結果、安定供給を実現しつつ取引先との信頼関係も強化しました。この事例はサプライチェーン全体の強靭化を目指す好例であり、飲食業や建設業など他業種にも応用可能な取り組みです。
◆取り組みの詳細はこちら
https://kyoujinnka.smrj.go.jp/case/53/
なぜ多摩地域の企業は今こそ備えるべきか
多摩川や浅川など複数の一級河川を抱える多摩地域は、台風や集中豪雨による河川氾濫のリスクが高く、さらに丘陵地や山間部では土砂災害の危険もあります。
例えば、2019年の台風19号では多摩川の水位が急上昇し、調布や府中、日野市の一部で住宅や事業所が浸水。物流網や工場操業にも影響が及びました。2023年の線状降水帯による豪雨でも、青梅市やあきる野市で土砂崩れや道路冠水が発生し、通勤や配送が長時間ストップしています。
一方で、多摩地域は首都圏西部の物流・製造・研究開発拠点として重要な役割を果たしており、一社の操業停止がサプライチェーン全体に波及する可能性があります。
特に中小企業は取引先への納期遅延や受注減が即座に経営危機につながるため、事業継続力の強化は単なる防災対策ではなく、地域経済全体の安定を守るための責務でもあります。
計画を“生きた武器”にする3つのポイント
事業継続力強化計画は、認定を受けただけでは十分に機能せず、実際に現場で動かすための工夫が欠かせません。そのためには「動かす」「維持する」「連携する」という3つの視点が重要です。
第1に、年1回の社内訓練を行い、計画通りに行動できるかを確認します。製造業であれば設備停止時の代替手順、小売業であればPOS障害時の販売対応などをシミュレーションし、訓練後に必ず振り返りを行い計画を改善します。
第2に、ITによる情報の二重化です。顧客データや会計情報をクラウドに保存し、定期的にバックアップを取ることで、システム障害や災害時にも業務を継続可能にします。権限管理やオフラインでの代替手段も併せて整えることが求められます。
第3に、取引先との相互支援協定を結ぶことです。資材や人員の融通を取り決め、協定は必ず文書化し、定期的に内容を更新します。こうした取り組みにより、計画は単なる「書類」から、実際に機能する「生きた武器」となり、災害時にも強い企業体制を築くことができます。
はじめの一歩
制度を知っているだけでは意味がありません。実際に行動に移した企業だけが、災害やトラブルが起きても「明日も動ける会社」でいられます。 まずは【自社内で組織を巻き込んで計画を進めるのか、それとも専門家と相談しながら進めるのか】を決めることが大切です。
もし「相談しながら考えたい」と思われたら、こちらの【ご相談フォーム】のリンクから必要事項を入力しお問合せください。
無料相談として対応いたしますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
プロフィール
梅澤 朗広
SDGusサポーターズ株式会社 代表取締役
日本JC公認SDGsアンバサダー
FC NossA八王子 アドバイザリーボード
大切にしている価値観:感謝・貢献・共創
野村證券、東京ヴェルディを経て2019年にSDGusサポーターズ株式会社を設立。SDGsの「持続可能な社会の実現」「誰一人とりのこさない」の理念に共感し、企業に対してCSV(共通価値の創造)の観点で事業活動と社会活動の両立に向けた経営サポートをおこなっています。SDGsと自社の活動に対する理解を深めてアクションを考えるワークショップや、様々なパートナーと連携して営業・広報・採用のサポートをおこなっています。
SDGsについて興味を持っている・相談したいなど、ぜひコチラにお気軽にお問合せください。


