「最近、天気がまったく読めないですよね」そんな声を建設業など外での仕事が多い方々からよく耳にします。「朝は晴れていたのに、午後になったら急に真っ黒な雲が出てきて大雨に降られた…」そんな経験、ありませんか?


突発的に発生する“ゲリラ豪雨”や広範囲を襲う“線状降水帯”。昔はあまり聞かなかったこれらの言葉が、今ではすっかり日常の会話に紛れ込んでいます。
ゲリラ豪雨とは、狭い範囲に短時間で猛烈な雨が降る現象のことです。一方で線状降水帯は、積乱雲が帯のように連なり、長時間にわたって激しい雨を降らせる現象を指します。
どちらも気候変動の影響を受けて年々増加しており、「いつか来るかもしれない」ではなく「いつ来てもおかしくない」災害リスクへと変わってきています。そして今、この変化は私たちの暮らしだけでなく、企業の経営そのものにも深刻な影響を与え始めています。
目次 ➖
気候変動は、経営にとって“リスク”になった

ここ数年で、気候変動は単なる環境問題ではなく、企業の経営リスクそのものに変わりました。
例えば、ソニー損保は2024年10月から火災保険の保険料率を全国平均で13%引き上げました。
しかも、地域の水災リスクに応じて5段階の細分化が導入され、浸水リスクの高いエリアでは大幅値上げ、逆にリスクが低い地域では少し下がるという、いわば“災害リスクの査定”が始まっています。
これまで一律だった保険料が、「どれだけ備えているか」や「どの場所に事業所があるか」で変わる時代になったのです。
つまり、自然災害は「いつか来るかもしれない出来事」ではなく、すでに企業コストや事業戦略に影響を与える、避けられない経営課題なのです。
いざという時の安心をつくる―企業に必要なBCPとは
こうしたリスクが増える中で、近年よく耳にするのがBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)です。

BCPとは、災害や事故、感染症、サイバー攻撃など予期せぬ事態が起きても、企業の重要業務をできるだけ止めず、早期に復旧させるための計画のことです。
たとえば、
- 大地震が発生したときに社員の安否確認や避難をどうするか
- 工場やオフィスが使えなくなったら、どこで業務を続けるか
- サイバー攻撃でシステムがダウンしたら、どの順番で復旧するか
こういった“いざという時のシナリオ”をあらかじめ決めておくことで、被害を最小限に抑え、顧客や取引先からの信頼を守ることができます。
BCPがあるかないかで、企業の立ち上がりスピードは大きく変わります。
実際、大規模災害後の企業調査では、BCPを策定していた企業は復旧が平均2倍早かったというデータもあります。つまりBCPは、大企業だけの話ではなく、中小企業にとっても「会社を守るリアルな道具」なのです。
まずは「ハザードマップ」を確認することから始めよう
BCPの第一歩としておすすめなのが、ハザードマップの確認です。
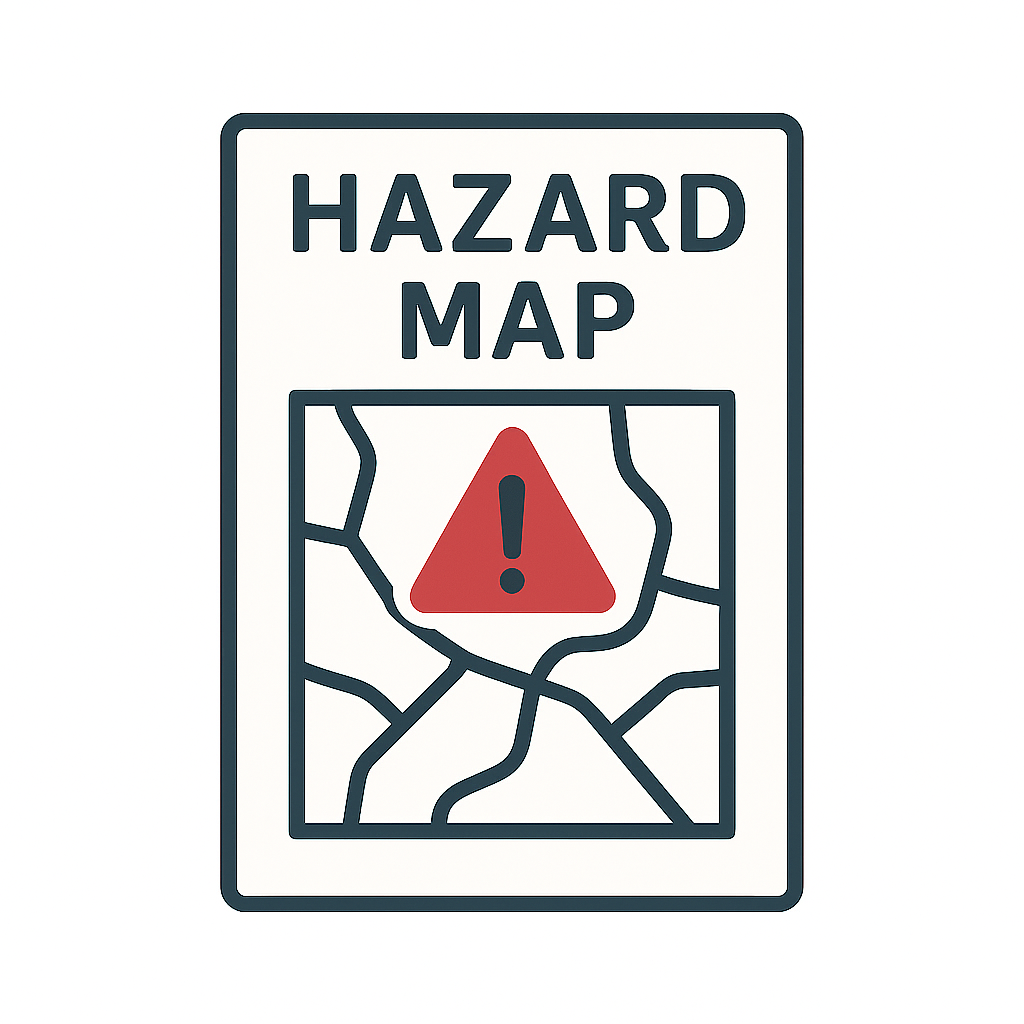
ハザードマップとは、市区町村が公開している、地域ごとの水害・地震・土砂災害リスクを地図上でわかりやすく示したものです。最近では、自治体のホームページや、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」(https://disaportal.gsi.go.jp/)から簡単に確認できます。
やり方はとてもシンプルです。
①サイトにアクセスして住所を入力する
②水害・土砂災害・地震など、見たい災害種別を選ぶ
③リスクが色分けされた地図を確認する
――この3ステップだけで、今いる場所や自社の拠点がどのくらい危険かがすぐに分かります。
例えば、工場や事業所が実は浸水リスクの高いエリアにあるとわかったら、
- 避難ルートを社員と共有する
- 重要な設備を2階以上に移す
- 書類やデータの保管方法を見直す
といった具体的な対策が検討できます。
こうした「事前の気づき」は、災害が起きてからでは取り返せません。
リスクを“見える化”することで、初めて企業として“動ける備え”が始まるのです。
では、ハザードマップ以外に、企業が特に意識しておくべきリスクにはどんなものがあるのでしょうか。
ハザードマップの次に確認しておきたい4つのリスク
BCP策定において特に意識しておきたい4つのリスクについて解説します。
1. 地震
日本では、地震による建物倒壊・停電・断水・通信途絶といった物理的被害が一瞬で起こりえます。
ある製造業では、震災後の1週間、工場機械が使えず数千万円の損失を出しました。
しかも、再開には現場確認や部品調達など、想像以上の時間がかかります。
2. 大雨・水害
ゲリラ豪雨や線状降水帯により、地域一帯が冠水するケースも。
特に物流や訪問サービスでは、道路の冠水だけで営業停止に追い込まれることもあります。
工場や事務所の浸水リスクは、事前のハザードマップ確認で大きく軽減できます。
3. 感染症
コロナ禍で実感した通り、“人が動けない”ことによる業務停止も深刻です。
紙書類中心の業務や、出社前提のシステム設計は非常時に脆く、在宅勤務への切り替えやクラウド移行はBCPの基盤となりつつあります。
4. サイバー攻撃
今やサイバー攻撃は、最も静かに、そして最も深刻な影響を及ぼす“見えない災害”です。
メールの添付ファイル1つで業務システムが完全停止し、復旧に数週間を要したという事例もあります。
無料ツールを活用しよう
地震については、所在地と建物構造を入力するだけで、地震時の倒壊リスクをすぐに診断できる「地震10秒診断」(https://nied-weblabo.bosai.go.jp/10sec-sim/)という、防災科学技術研究所が提供する無料ツールがオススメです。
ある町工場では、この診断で「全壊の恐れあり」という結果が出たことをきっかけに耐震補強を実施。
今では地域の避難拠点としても信頼されています。
こうした見える化は、BCP計画書の“根拠資料”としても活用できます。
最新情報は“気象のプロ”からキャッチしよう
BCPの第一歩は「備えること」ですが、そのためには“情報の速さ”も欠かせません。
そこでおすすめなのが、YouTubeの「ウェザーニュース」公式チャンネル(@weathernews)です。
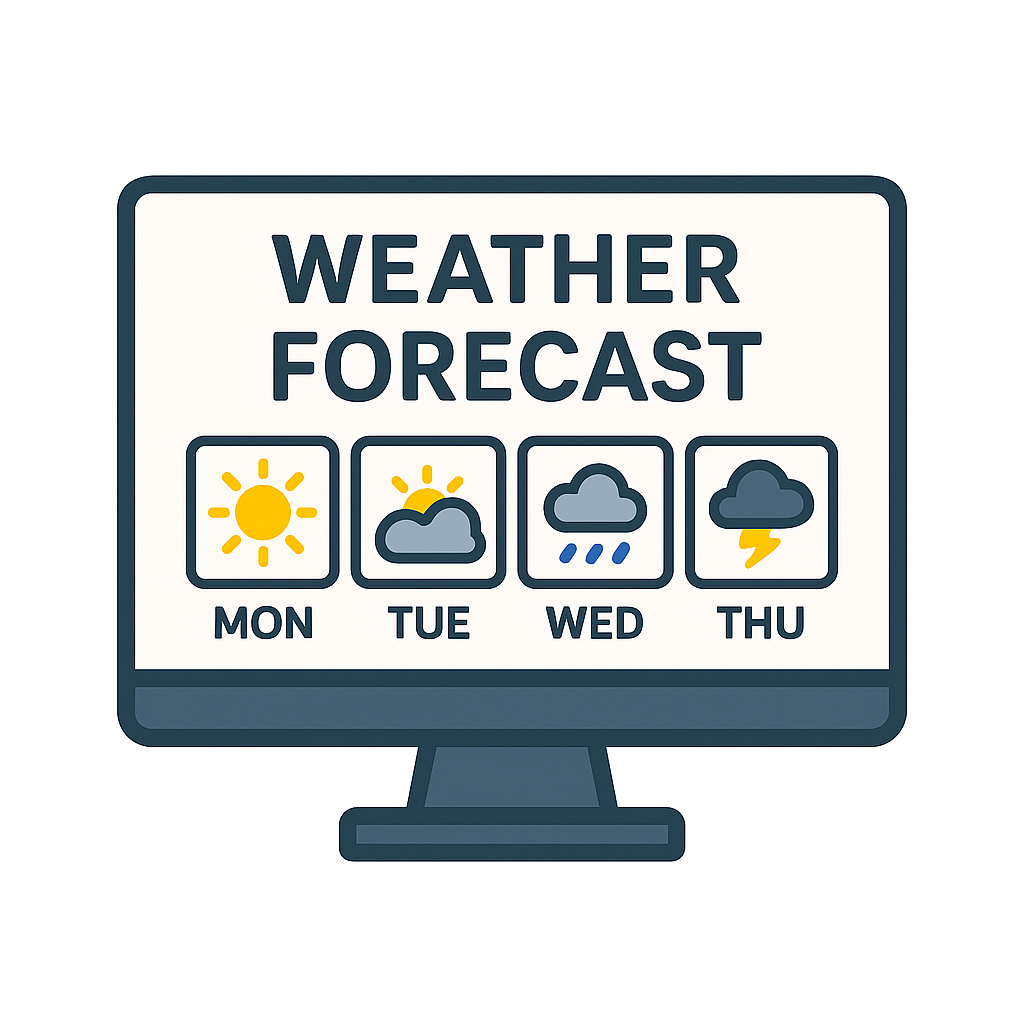
このチャンネルでは、全国の気象レーダーやライブ映像をもとに、リアルタイムで天気の変化や災害リスクを解説してくれます。 専門の気象キャスターが、難しい言葉を使わずにわかりやすく解説してくれるのと、「あと1時間でどこに大雨が来るか」など、現場判断に直結する情報をタイムリーに把握できます。
移動中のスタッフがスマホで確認できるのも大きなポイントです。
“早めに知って、早めに動く”。
その行動のために、こうしたツールをぜひ活用してみてください。
「備え」は社員への最大のエールになる
BCPは単なる業務マニュアルではありません。
社員の命を守る計画であり、「この会社なら大丈夫」という信頼を生む経営の柱です。
言い換えれば、災害に強い会社づくりは、“人に優しい経営”のかたちです。
SDGsでも「住み続けられるまちづくり」が掲げられています。
BCPは、まさにその実践です。
情報の整理、体制づくり、ツールの活用――
一つずつでいいので、あなたの会社に合った備えを始めてみましょう。
その小さな一歩が、きっと未来を守る力になります。
プロフィール
梅澤 朗広
SDGusサポーターズ株式会社 代表取締役
日本JC公認SDGsアンバサダー
FC NossA八王子 アドバイザリーボード
大切にしている価値観:感謝・貢献・共創
野村證券、東京ヴェルディを経て2019年にSDGusサポーターズ株式会社を設立。SDGsの「持続可能な社会の実現」「誰一人とりのこさない」の理念に共感し、企業に対してCSV(共通価値の創造)の観点で事業活動と社会活動の両立に向けた経営サポートをおこなっています。SDGsと自社の活動に対する理解を深めてアクションを考えるワークショップや、様々なパートナーと連携して営業・広報・採用のサポートをおこなっています。
SDGsについて興味を持っている・相談したいなど、ぜひコチラにお気軽にお問合せください。


