「梅澤朗広の採用SDGs」第14回目は、「脱炭素経営の社内浸透を加速する方法 ― 社員を巻き込む5つの工夫」です。
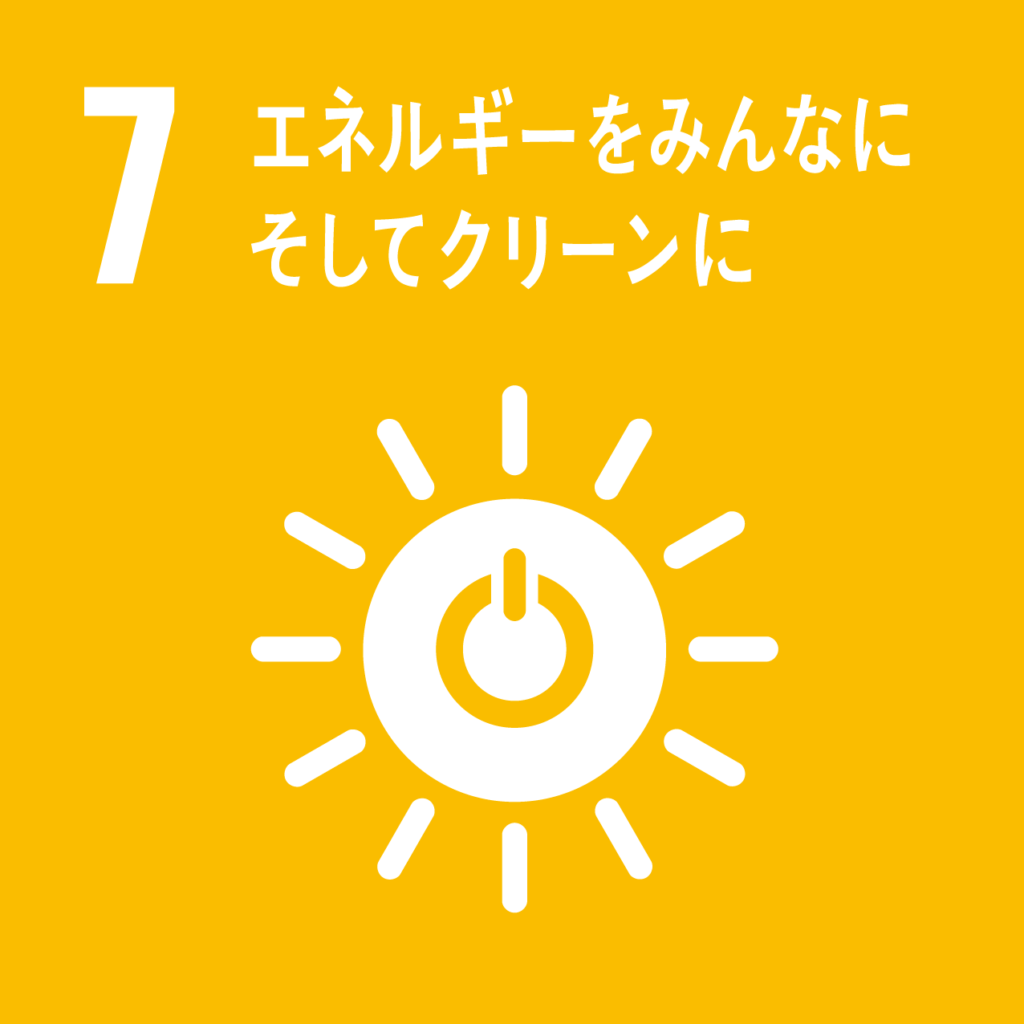



最近こんな声をよく耳にします。
「うちは脱炭素経営に取り組もうとしてるけど、社員がピンとこないのか、反応がいまいちなんだよね…」
「トップである自分だけが熱くて、なんだか浮いてる感じがしてきた…」
そんなふうに感じていたら、今日はちょっと参考になる話をしてみたいと思います。
テーマは、社員を巻き込んで“自分ごと”にしていくための5つの工夫です。
目次 ➖
よくあるアドバイス:「経営者が強いメッセージを発信しましょう」
もちろん、それも大事です。トップが真剣じゃないと始まらない、というのは間違いありません。
でも、経営者がいくら熱く語っても、社員の顔が「……」となるの、よくあることです。
特に「GX(グリーントランスフォーメーション)」や「カーボンニュートラル」って、正直難しそうで、遠い話に聞こえがちなんですよね。
社員が自然と参加したくなる5つの工夫
今回ご紹介するのは、実際に企業で成果が出ている具体的な取り組みです。
共通しているのは、「楽しく」「仲間と」「目に見えるかたちで」取り組んでいるという点です。
社員の巻き込みって、無理やりやらせることではないんです。自然と参加したくなる空気をつくることなんですよね。
ゲーム形式で学ぶ ―「座学よりずっと楽しい」
静岡県の印刷会社「株式会社アイエルシー」では、脱炭素経営の理解を深めるために、“体験型の脱炭素カードゲーム”を社内研修に導入しました。これは、社員がいくつかのチームに分かれて、仮想の企業を経営しながら「再生可能エネルギーへの投資」「省エネ機器の導入」「環境配慮型商品の開発」など、リアルな経営判断を行っていくゲームです。
各チームはゲーム開始時に自社のビジョンや経営スタイルを選択し、それに応じたキャラクターや初期資源が与えられます。キャラクターには、それぞれ独自の“特殊スキル”があり、「社長=鶴の一声でプロジェクトを1段階進められる」「ベテラン社員=プロジェクト達成の社内理解度を1段階パワーアップさせる」など個性豊か。環境イベントや顧客からの要望などのイベントが次々と発生し、それにどう対応するかでチームの“売上”や“社会的評価”が変動する仕組みになっています。
「自分の判断で環境投資をして利益が伸びたとき、達成感がすごかった」「最初は意味がわからなかったGXやカーボンニュートラルの考え方が、ゲームを通じて腑に落ちた」といった声が続出。普段は業務で関わることのない他部署のメンバーと協力しながら戦略を練ることで、自然と社内の一体感も生まれました。
特に印象的だったのは、ゲーム終了後に社員同士が「これ、うちの会社でも実際にできそうじゃない?」「うちの部署でもエネルギー使用量って減らせるかも」といった現実の業務への応用を語り始めたこと。単なるレクリエーションで終わらせず、行動変容のきっかけになることが、このゲーム最大の魅力です。
結果として、社員の中に「脱炭素は会社のためだけじゃなく、社会や次世代のためにもなるんだ」という意識が芽生え、社内プロジェクトの提案や取引先との商談にも前向きな変化が表れたそうです。まさに“楽しく、気づきと行動を引き出す”学びの場が生まれています。
チーム制で「ほんの少しの競争」を

新潟県の製造業「広一化学工業」では、脱炭素経営の第一歩として、社内の電力使用量の“見える化”に取り組みました。そして、ただデータを共有するだけでなく、「ちょっとしたゲーム感覚」を加えることで、社員の意識を自然に高める工夫をしています。
取り組みの中心は、部署ごとに電気使用量の削減目標を立てる“チーム対抗エコチャレンジ”。毎月の電力使用量を集計し、最も削減幅が大きかったチームを社内で発表するというシンプルな仕組みですが、社内にちょっとした「前向きな競争心」と「仲間意識」が生まれました。
このチャレンジのユニークなポイントは、“ごほうびの温度感”にあります。勝ったチームには、なんと社長自らコンビニで選んだスイーツを手渡しで差し入れ。プリンやエクレア、季節限定の和菓子など、内容は月ごとに変わり、「今月はどれかな?」と社員の間でちょっとした話題にもなっているそうです。
「来月はプリンじゃなくてアイスがいいな~」「あの部署には負けたくない!」といった軽いやりとりが自然と生まれ、オフィス内の空気もどこか和やかに。強制的な取り組みではなく、楽しさと達成感が絶妙なバランスで混ざり合い、社員から「次はうちが1位を取りたい!」という声が自発的に上がるようになりました。
さらに、副次的な効果として、「節電のためにどの機械を止めればいいか」「会議室の照明をLEDにしたらどうか」といった改善提案も各チームから出るようになり、ただのゲームで終わらない“現場発の工夫”が広がっています。
このように、小さなごほうびとチーム制を掛け合わせることで、社員のやる気を引き出し、脱炭素への第一歩を「自分たちの楽しみ」に変えてしまった事例です。地道な取り組みも、ちょっとした遊び心で続けられるものに変えられるのですね。
表彰制度で「意味を持たせる」

どんなに小さな取り組みでも、それが誰かに認められると「やってよかった」と感じられるものです。特に、環境への取り組みのように目に見える成果が出にくいテーマでは、「行動に意味を持たせる」仕掛けがとても重要になります。
秋田県の「株式会社コンダクター」では、そうした観点から「脱炭素チャレンジ賞」というユニークな社内表彰制度を導入しました。対象となるのは、日々の節電や廃棄物の削減、再利用アイデアの実践など。業務の中で社員が自発的に取り組んだ“環境にやさしい行動”を、社内掲示板やミーティングで共有し、その中から月に一度、特に効果的だった事例を表彰しています。
賞状は手書きのメッセージ入りで、社長から直接手渡しされます。受賞者にはその場で「ありがとう、君の行動が社内全体の意識を変えてくれた」といった声がかけられることもあり、ちょっとした感動の時間になっているそうです。
ある社員は、会社でもらった賞状を家に持ち帰り、家族に見せたところ、お子さんが「学校でもエコの勉強したよ!パパすごいね!」と目を輝かせて喜んでくれたそうです。「あの瞬間、自分の仕事が社会とつながっていると実感できた」とその社員は語ります。
また、この表彰をきっかけに「うちの部署でも、コピー用紙の裏紙活用ルールを作ってみよう」「休憩室の照明をタイマー式に変えたらどうか」など、他の社員にも新しい提案が広がっていきました。自分の行動が評価されることで、次の行動のきっかけになる。その連鎖が、社内全体の脱炭素マインドを少しずつ育てているのです。
表彰制度というと、つい堅苦しい印象になりがちですが、株式会社コンダクターのように“あたたかさ”と“意義”を両立させることで、社員一人ひとりの取り組みに「意味」を感じてもらうことができるのです。評価は報酬だけでなく、「あなたの行動は価値がある」というメッセージなんですね。
社内報で「なぜやるのか」を繰り返す

人は一度聞いただけでは、なかなか本質を理解したり、行動に移したりはできません。特に「脱炭素経営」のような少し抽象的で中長期的なテーマは、繰り返し丁寧に伝えることで、ようやく「自分ごと」として腹落ちしていくものです。
静岡県の「株式会社ワイエス」では、その“伝え方”に工夫を凝らしています。月に1回発行される社内報には、毎号必ず「脱炭素経営」の特集ページがあり、二酸化炭素排出量の推移や、最新の省エネ設備の紹介、補助金情報などが、イラストや写真を交えて分かりやすく紹介されています。
たとえば、ある号では「今月の脱炭素トピック」として、社員食堂の電気をLED照明に切り替えた効果をグラフで解説。削減できたCO₂の量を「杉の木〇本分に相当」と例えたことで、「目に見える成果」として社員の印象に残ったそうです。
さらに注目すべきは、社長自ら執筆する「コラム」欄の存在です。そこでは、ただ脱炭素を推進しようという呼びかけだけではなく、「この取り組みが、あなたの働き方やキャリアにどうつながるのか」に踏み込んで書かれています。
ある回では、「将来的に環境に配慮した企業が選ばれる時代になる。だからこそ、今この会社で脱炭素を学んでおくことが、あなた自身の市場価値を高めることになる」と語られており、社員の心にも響いたとのこと。「環境のため」というだけでなく、「自分の未来のため」という視点で捉える社員が増えてきているそうです。
このように、社内報は単なる情報伝達ツールではなく、「会社がどこへ向かおうとしているのか」「なぜその道を選ぶのか」を繰り返し共有する“コンパス”のような役割を果たしています。読んだ社員が「なるほど、だからこの活動をやっているんだ」と納得し、行動の裏にある意味を理解できるからこそ、自発的な取り組みが少しずつ増えていくのです。
小さな紙面でも、丁寧に「なぜ」を重ねていくことで、社内の空気が少しずつ変わっていく。そんな“地道な広報”が、脱炭素経営を支える大きな力になっているのです。
巻き込み成功のカギは“関わっている感”
脱炭素経営を“押し付け”ではなく、“仲間と取り組むプロジェクト”にできた企業は、社内の雰囲気がガラッと変わります。
「みんなでやってる」「自分も関われている」
そんな感覚が芽生えると、不思議と前向きな声が出てくるんです。
そして、「なぜやるのか」が腹落ちすると、社員の行動が変わります。「なにを」ではなく、「なぜ」を伝えることで、巻き込み方も変わります。社員と一緒に汗をかく感覚は、間違いなく脱炭素経営の成功の鍵になるはずです。
やる気を引き出す“しくみの力”
社員のやる気や参加意欲は、気合や熱意だけでは続きません。
「一緒に考える」「声を取り入れる」「ちょっと楽しい」
そんな仕組みづくりこそが、脱炭素経営を支える土台になります。
今日の内容が、あなたの会社で“ちょっといい空気”を生み出すヒントになればうれしいです!
プロフィール
梅澤 朗広
SDGusサポーターズ株式会社 代表取締役
日本JC公認SDGsアンバサダー
FC NossA八王子 アドバイザリーボード
大切にしている価値観:感謝・貢献・共創
野村證券、東京ヴェルディを経て2019年にSDGusサポーターズ株式会社を設立。SDGsの「持続可能な社会の実現」「誰一人とりのこさない」の理念に共感し、企業に対してCSV(共通価値の創造)の観点で事業活動と社会活動の両立に向けた経営サポートをおこなっています。SDGsと自社の活動に対する理解を深めてアクションを考えるワークショップや、様々なパートナーと連携して営業・広報・採用のサポートをおこなっています。
SDGsについて興味を持っている・相談したいなど、ぜひコチラにお気軽にお問合せください。


