<第5回> 信頼関係の第1歩!1on1ミーティングの効果的な活用法
TAMA WORKをご覧の皆さん、こんにちは。採用定着士/社会保険労務士の高木です。
「採用と定着で中小企業の発展を支援する」をミッションとして、多摩地域を中心とした中小企業のサポートをさせていただいております。
この記事では「せっかく採用したのに…を防ぐ!社員が定着する職場づくりのポイント」と題して、
「採用はできたが、すぐ辞めてしまう・・・」
「定着率を上げたいが、どうしたらよいかわからない・・・」
といった人材定着にお悩みを持つ中小企業経営者、人事担当者、管理職の皆さんに役立つ内容を連載でお届けします。
5回目の今回は「信頼関係の第1歩!1on1ミーティングの効果的な活用法」についてお伝えします。
はじめに
社員の定着や成長を促すうえで、直属の上司との関係性は非常に大きな影響を及ぼします。日常業務の中では伝えきれない思いや不安、成長の方向性を共有するために、1on1ミーティングは極めて有効です。
とくに中途採用者にとっては、入社直後から「自分はここでやっていけるのか」「期待に応えられるのか」といった不安を抱えています。こうした不安を解消し、定着へと導くために、1on1ミーティングを活用します。ここでは、1on1ミーティングを定着にどう活かすか、効果的な運用方法を紹介します。
なぜ1on1が定着に効果的なのか?
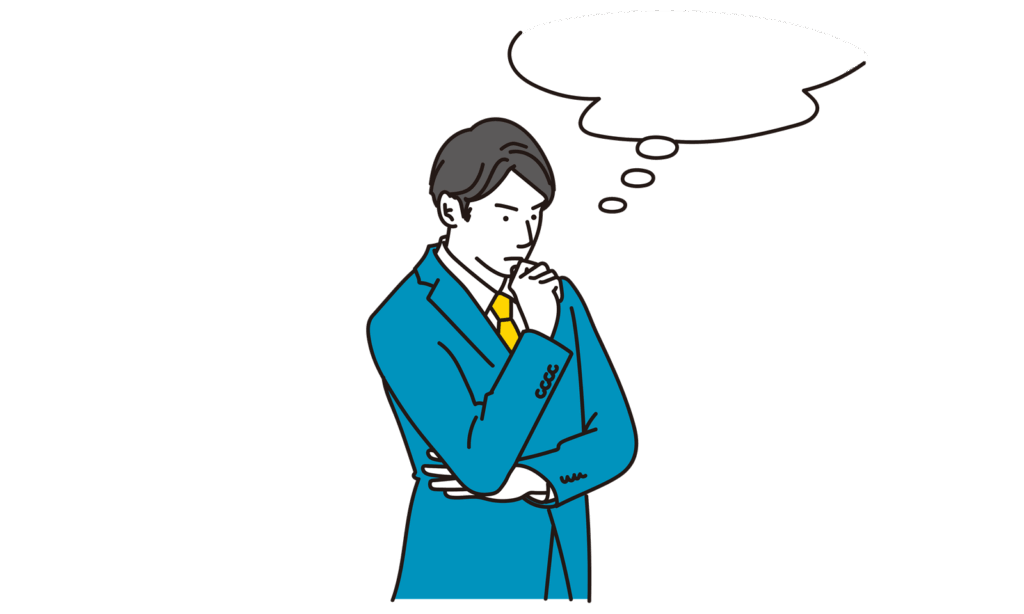
1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に1対1で対話する時間を設け、業務の進捗だけでなく、悩みやキャリアの方向性などを確認・共有する仕組みです。特に中途採用者にとっては、以下の点で効果があります。
・業務の進め方や組織文化に対する疑問・不安を気軽に相談できる
・自分の取り組みが上司に見てもらえているという「承認」を感じられる
・自分の将来像や目標を共有し、会社の方向性とすり合わせができる
このように、1on1ミーティングは「理解」「承認」「方向性の共有」という3つの側面から、中途採用者の定着を支える仕組みといえます。
入社から定着までの1on1ミーティングのステップ

❶入社~2週間程度
この時期は、「受け入れられている」「話を聴いてもらえる」という心理的安全性を築くことが最優先です。
歓迎の言葉に加え、日々の些細な出来事でも上司が話を聴き、承認することが信頼の土台を築きます。
例「初日から丁寧に取り組んでくれていてありがたいです」「わからないことを率直に聴いてくれて助かります」などの承認メッセージを伝える
❷入社3週目〜2カ月程度
業務に慣れてきた一方で、不安やギャップが浮き彫りになりやすいこの時期には、1on1の頻度と質が重要になります。
・週1回程度の頻度で、悩み・課題・人間関係について深く対話する
・成果や行動を具体的に承認し、小さな成功体験を後押しする
上司は「聴く」姿勢に徹し、部下が思っていることを安心して話せる雰囲気をつくることがポイントです。
❸入社3カ月目~
本人が「ここで長く働けるか」を判断するタイミングです。この段階では、次のような未来に向けた対話により、前向きな気持ちを育てていきます。
・これから挑戦したいことについて聴く
・スキルアップの方向性をすり合わせ
・本人の得意なことや強みを上司が理解し、活かせる場面を一緒に考える
1on1ミーティングの基本的な流れ

効果的な1on1ミーティングを行うためには、流れを押さえておくことが大切です。以下は具体的な流れの一例です。
❶アイスブレイク
雑談や最近の出来事について触れ、リラックスした雰囲気を作る
❷近況確認(傾聴)
業務の進捗や気になっていること、困っていることなど部下の話をとにかく聴く
❸成果や行動の承認
部下が行った工夫や貢献に対して、具体的に承認の言葉をかける
❹課題と解決策の共有
悩みや課題を一緒に整理し、解決に向けたアクションや上司の支援を考える
❺まとめ
内容を振り返り、次回までのアクションを確認する
このように、単なる業務報告ではなく、承認と対話を中心に構成することで、信頼関係が強化され、定着や成長につながっていきます。
1on1を成功させる3つのポイント
目的は「承認」と「対話」
1on1は業務の報告会ではなく、あくまで部下の声に耳を傾ける場です。
とくに中途採用者の場合、「自分のやり方で通用するか」「馴染めているか」といった不安があるため、評価よりも“理解”や“承認”を求めているケースが多いです。
ポイントは、具体的な行動に対してしっかり言葉で承認すること。「〇〇の対応は助かった」「その資料のまとめ方は分かりやすかった」など、具体性を持って伝えることが信頼関係の構築につながります。
形式よりも「頻度」と「継続性」
理想は週1回、難しくても隔週など、定期的に実施することが効果的です。
時間は30分程度で、なるべく落ち着いた場所で実施するのが望ましいです。
実施を支える仕組みづくり
1on1をスムーズに継続・運用するためには、上司が迷わず対応できるような“仕組みづくり”が欠かせません。たとえば、1on1で使用する質問例や会話の流れをまとめた運用マニュアルを事前に用意しておくと、初めて実施する上司でも安心して臨むことができます。
ありがちな失敗例とその対策
1on1を形だけで行ってしまうと、逆に信頼を損ねる結果となります。
・業務報告だけで終わってしまう
・上司が一方的に話す場になっている
・約束した面談を何度もキャンセルしてしまう
このような状態では、「本当は聴いてもらえていない」「自分には関心がないのでは」と中途採用者に不信感を与えてしまいますので気をつけましょう。
まとめ
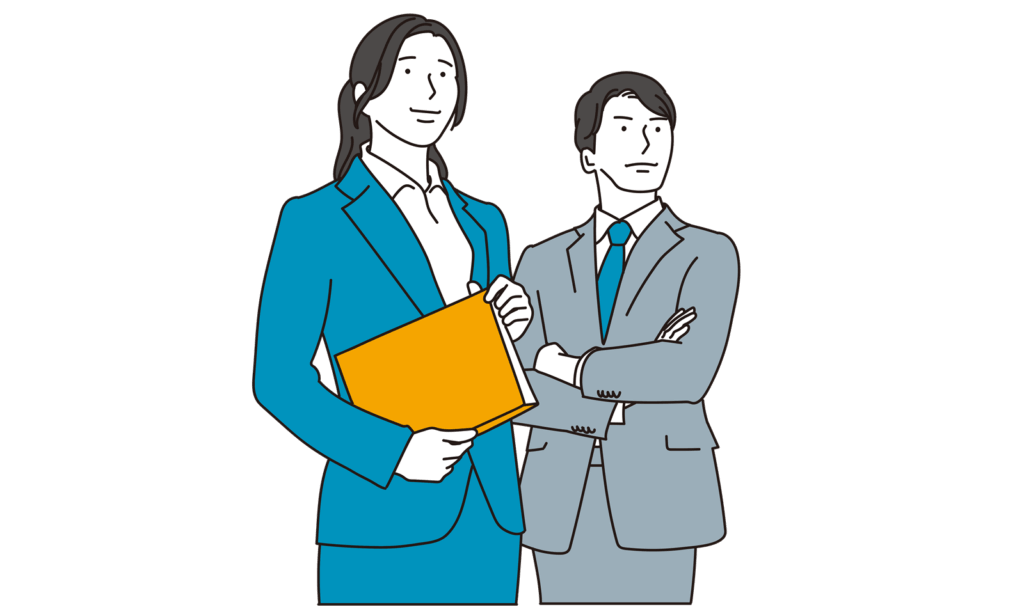
中途採用者にとって、直属の上司を信頼できるかどうかが、定着に直結します。その信頼関係を築くための有効な手段が、定期的な1on1ミーティングです。単に面談を実施するだけではなく、「承認」「共感」「将来のすり合わせ」を意識した対話を、入社から定着の各フェーズで積み重ねることが大切です。
1on1ミーティングは、一過性の取り組みではなく、人材定着と成長を支える「継続的な対話のプロセス」なのです。
プロフィール
社労士事務所CRAFT 代表
採用定着士/特定社会保険労務士 高木 厚博(たかぎ あつひろ)
1974年大阪生まれ。私立清風高校、関西大学法学部卒業。大手外食企業にて、店舗管理等を経験。
退職後バイトをしながら試験勉強をし、社会保険労務士試験合格。地域最大級の社労士事務所に勤務。約15年勤務したのち2019年11月独立開業。顧問先企業の人事・労務の課題解決に取り組む一方、「採用と定着で中小企業の発展を支援する」をミッションに、採用支援、賃金制度・評価制度構築、「パワハラ予防研修」や「承認力向上研修」などの社内研修で中小企業の社員の定着・育成を支援している。
金融機関、商工会議所主催セミナーなど講演実績多数。パワハラ予防士。承認ファシリテーター。
著書「うちはいい会社です!と社員から言われる就業規則25のチェックポイント」(共著、泉文堂)。
NHK総合テレビ「おはよう日本」『103万の壁 企業の足かせ』出演。
好きな飲み物:よなよなエール 好きな食べ物:天下一品こってり
【連絡先】
〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮1-26-7 ラミアール聖蹟508


