<第3回>入社1週間がカギ!オンボーディングの重要性
TAMA WORKをご覧の皆さん、こんにちは。採用定着士/社会保険労務士の高木です。
「採用と定着で中小企業の発展を支援する」をミッションとして、多摩地域を中心とした中小企業のサポートをさせていただいております。
この記事では「せっかく採用したのに…を防ぐ!社員が定着する職場づくりのポイント」と題して、
「採用はできたが、すぐ辞めてしまう・・・」
「定着率を上げたいが、どうしたらよいかわからない・・・」
といった人材定着にお悩みを持つ中小企業経営者、人事担当者、管理職の皆さんに役立つ内容を連載でお届けします。
3回目の今回は「入社初日がカギ!オンボーディングの重要性」についてお伝えします。
はじめに
せっかく採用した社員がすぐに離職してしまう・・・そんな悩みを抱えている会社は少なくありません。今年4月の新入社員がすでに退職してしまった、という話も聞きます。
「職場に合わなかったのだろう」と片づけてしまっては、いつまでも定着しない採用が続いてしまうかもしれません。 定着のカギを握るのが「オンボーディング」です。特に中途採用者の場合、入社から3か月程度が「辞めるか・続けるか」の分かれ道になります。今回は、オンボーディングの目的から具体的な取り組み方までを解説します。
オンボーディングとは?

オンボーディングとは、「乗り物に乗る」ことを意味する「on-board」から派生した言葉で、新しく入社した社員が会社にスムーズに馴染み、早期に戦力として活躍できるようにする一連の支援プロセスのことを指します。具体的には、受け入れ体制の整備、教育プログラム、業務サポート、人間関係の構築支援などが含まれます。
オンボーディングの目的と重要性
オンボーディングの目的は大きく3つあります。
① 早期離職を防ぐこと
② 業務への早期の適応を促すこと
③ 企業文化や職場に馴染んでもらうこと
特に中途採用者は即戦力を期待されることが多いため、教育や支援が手薄になりがちです。しかし、どれほど経験がある人でも、新しい会社には不安を抱えて入ってきます。業務の進め方や職場の雰囲気、暗黙のルールなど、入社後のフォローがなければ「想像と違った」と早期離職につながってしまいます。

中途採用者の離職を防ぐオンボーディングの取り組み
では、具体的にどのような取り組みが効果的なのでしょうか。以下の3つの視点で進めると効果的です。
安心して過ごせる雰囲気をつくる
入社初日に「歓迎されていない」と感じてしまえば、その後の業務への意欲も下がってしまいます。歓迎の声掛けや、オリエンテーション資料の準備、自己紹介の機会を設定するなど、ちょっとした配慮で「この会社に入って良かった」と感じてもらえるかどうかが決まります。
社内ルールや業務フローの明文化
「聞けば教えてもらえる」というスタンスではなく、「知らなくて困ること」を事前に伝えておく姿勢が大切です。就業規則の説明、使用するツールの操作マニュアル、1日の仕事の流れなど、文書やチェックリストで見える化しておくことで、混乱や不安を軽減できます。
業務だけでなく人間関係にも配慮
配属先の上司や先輩だけでなく、社長・役員や他部署とも挨拶を交わす機会をつくるなど、周囲との関係づくりを支援することも大切です。「誰に何を聞けばいいかわからない」という状態は、孤立感と不安を生みます。メンター制度や、1on1(1対1の定期面談)なども効果的です。
「現場任せのOJT」では不十分
多くの中小企業では、OJT(On the Job Training=現場での実地指導)に任せきりのケースが見られます。しかし、OJTだけでは以下の問題が発生します。
① 指導担当者によって教え方や内容にばらつきが出る
② そもそも「何を」「いつまでに」覚えるかが不明確
③ 指導する側も通常業務で手一杯になり、フォローが不十分になる
このような状態では、新入社員は常に「このやり方で合っているのか?」「何を求められているのか?」という不安の中で仕事を進めることになります。だからこそ、あらかじめ体系的な教育プログラムを用意しておく必要があるのです。
教育プログラムの作成がカギ!1週間の計画を立てよう
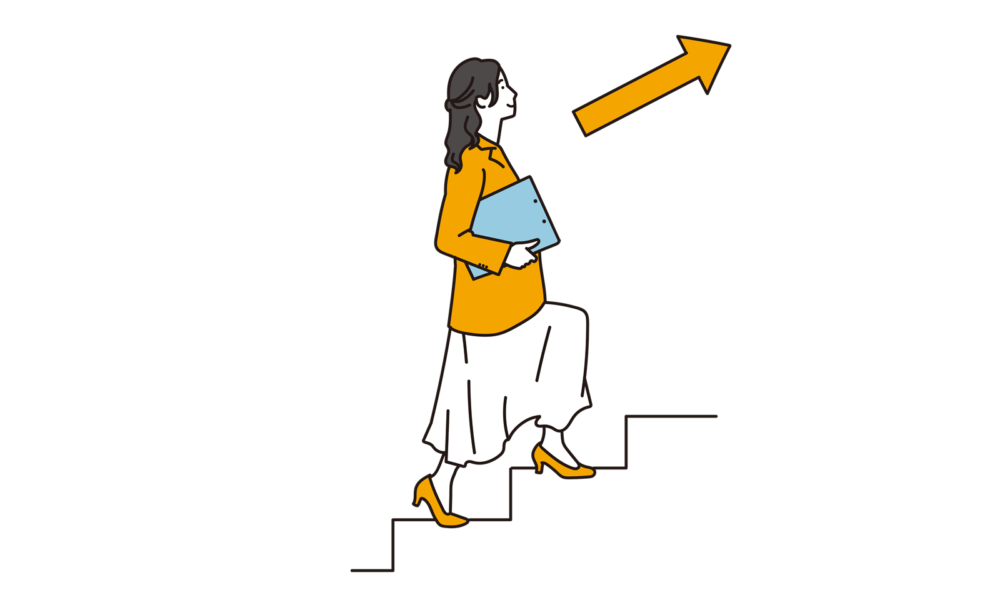
オンボーディングの第一歩として、まずは「1週間の教育プログラム」を作成することをおすすめします。「仕事を身に付ける」のではなく、「安心して業務に入っていける状態」をゴールにします。
プログラム作成のポイントは次の通りです。
① 1日ごとの到達目標を設定する
② 理解度に応じて調整できる余白を持たせる
③ 座学と実務のバランスをとる
④「振り返り」や「質問・相談」の時間を設ける
以下は、1週間の教育プログラム例です。
1週間オンボーディングプログラム(例)【事務職向け】
| 日程 | 主な内容 |
|---|---|
| 1日目 | ・歓迎あいさつ/会社案内 ・社内ルール・就業規則の説明 ・自己紹介の機会設定 ・社内ツアー、備品・PCの案内、メール・システム初期設定 ・振り返り面談 |
| 2日目 | ・使用システムの操作説明(会計ソフト、社内チャット等) ・ファイル保存ルール、文書管理方法の習得 ・業務マニュアルの確認 ・簡単なデータ入力作業のトレーニング ・振り返り面談 |
| 3日目 | ・簡単なデータ入力作業の実践 ・簡単な文書作成業務のトレーニング ・振り返り面談 |
| 4日目 | ・簡単なデータ入力作業と文書作成業務の実践 ・電話応対のポイント説明とロールプレイ ・振り返り面談 |
| 5日目 | ・簡単なデータ入力作業と文書作成業務の実践 ・電話応対の復習と実践 ・これまでの業務の復習とまとめ ・振り返り面談(5日間の総括と今後の支援方針確認) |
入社1週間目のプログラムでは、「職場に受け入れてもらえた」と感じ、次の1週間も安心して仕事に取り組めそうだと思える状態をつくることが大切です。
まとめ
オンボーディングは、新入社員が職場に早く馴染み、安心して長く働き続けてもらうために大切な取り組みです。「この会社でやっていけそうだ」と思ってもらえるよう、計画的に受け入れ体制を整えましょう。教育プログラムの整備は時間も手間もかかりますが、結果的に社員の定着率や戦力化スピードの向上につながる投資です。ぜひ取り組んでみてください。
プロフィール
社労士事務所CRAFT 代表
採用定着士/特定社会保険労務士 高木 厚博(たかぎ あつひろ)
1974年大阪生まれ。私立清風高校、関西大学法学部卒業。大手外食企業にて、店舗管理等を経験。
退職後バイトをしながら試験勉強をし、社会保険労務士試験合格。地域最大級の社労士事務所に勤務。約15年勤務したのち2019年11月独立開業。顧問先企業の人事・労務の課題解決に取り組む一方、「採用と定着で中小企業の発展を支援する」をミッションに、採用支援、賃金制度・評価制度構築、「パワハラ予防研修」や「承認力向上研修」などの社内研修で中小企業の社員の定着・育成を支援している。
金融機関、商工会議所主催セミナーなど講演実績多数。パワハラ予防士。承認ファシリテーター。
著書「うちはいい会社です!と社員から言われる就業規則25のチェックポイント」(共著、泉文堂)。
NHK総合テレビ「おはよう日本」『103万の壁 企業の足かせ』出演。
好きな飲み物:よなよなエール 好きな食べ物:天下一品こってり
【連絡先】
〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮1-26-7 ラミアール聖蹟508


