TAMA WORKをご覧の皆さん、こんにちは。採用定着士/社会保険労務士の高木です。
「採用と定着で中小企業の発展を支援する」をミッションとして、多摩地域を中心とした中小企業のサポートをさせていただいております。
この記事では「せっかく採用したのに…を防ぐ!社員が定着する職場づくりのポイント」と題して、
「採用はできたが、すぐ辞めてしまう・・・」
「定着率を上げたいが、どうしたらよいかわからない・・・」
といった人材定着にお悩みを持つ中小企業経営者、人事担当者、管理職の皆さんに役立つ内容を連載でお届けしています。
第8回の今回は「社員の定着は“未来の見える化”から!キャリアパスで育てる仕組み」についてお伝えします。
はじめに

中途採用でせっかく入社してくれた社員が、半年や1年足らずで辞めてしまう——。多くの中小企業が抱える悩みです。その理由を聞いてみると、「キャリアのイメージが湧かない」「この先、成長できる気がしなかった」といった声がよく返ってきます。
このように“この会社でどう成長していけるのかが見えない”という不安が、離職につながっているのです。
1.キャリアパスとは?~社員に「未来の地図」を見せるもの~
キャリアパスとは、社員がこれからどんな役割を担い、どのような知識・スキルを身につけ、どんな成長ができるのかを、段階的に示した“将来の道しるべ”です。
これがないと、「この仕事を続けていけば、どんな力がつくのか」「5年後、10年後の自分はどうなっているのか」が見えず、日々の業務がただの作業に感じられてしまいます。
キャリアパスがあることで、「今の業務をしっかり身につけたら、次はこういう仕事を任せてもらえる」「このステップを踏めばリーダーになれる」と、目標を持って前向きに働くことができるのです。
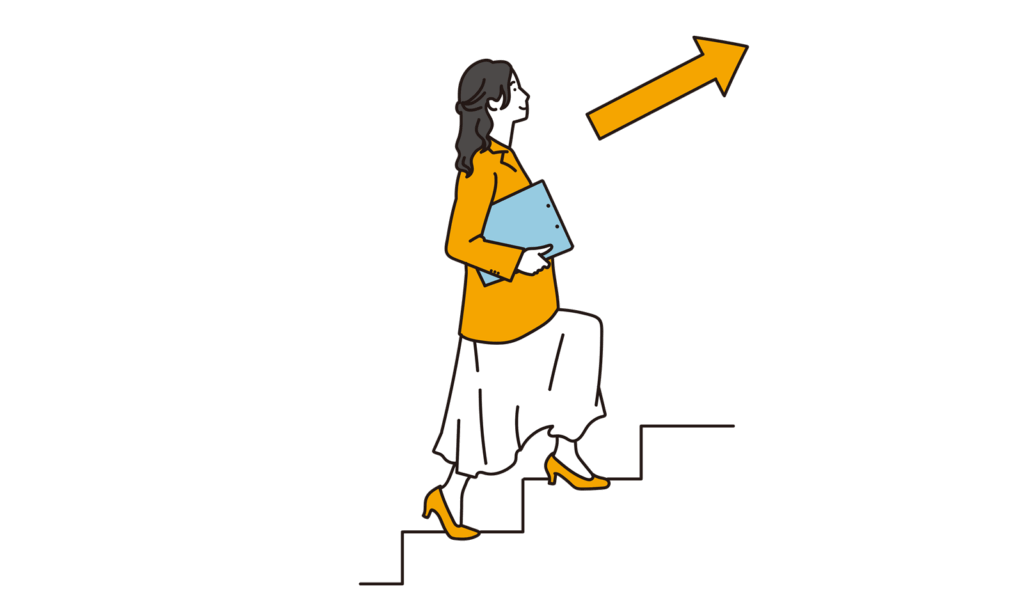
2.役割ベースで考える、シンプルなキャリアパスのつくり方
小規模な企業でも取り組みやすいキャリアパスの作成方法として、「役割」をベースに設計することをおすすめします。
たとえば製造業であれば、以下のようにステップを描けます。
【レベル1】決められた工程を正確にこなす
【レベル2】複数の工程を任せられる
【レベル3】作業手順の改善提案ができ、後輩への指導を行う
【レベル4】生産全体の流れを見ながら判断する
このように、社員の成長段階を「どんな役割を担えるようになるか」という視点で整理することで、キャリアパスを描きやすくなります。
さらに、それぞれのステップに対して「どんな知識・スキル・経験が求められるのか」を併せて示すことで、社員自身が「自分は今この段階にいて、次のステップに進むために何を身につければいいのか」が明確に理解できるようになります。
3.日常業務の中でキャリアパスを活かすには
せっかく作成したキャリアパスも、社員に伝わっていなければ意味がありません。「説明会で伝えたけれど、すぐに忘れられてしまった」というケースもよくあります。
そこで、次のような工夫が効果的です。
(1)紙1枚にまとめて配布し、定期的に見直す
たとえば、A4用紙1枚にまとめてファイルやデスク周りに置けるようにしたり、職場の掲示板などに貼っておいたりすることで、常に意識づけができます。

(2)OJTの現場で活用する
実務を通じて育てるOJT(On the Job Training)において、「今のあなたのステージはここ」「この業務をマスターできれば次のステップに進める」といった対話を繰り返すことで、キャリアパスが「生きたもの」として機能します。
(3)定期面談でのPDCA運用につなげる
少なくとも年に1回はキャリアパスに沿って、「次年度にどのステップを目指すのか」「そのためにどんな業務や取り組みをするか」を上司と一緒に目標設定します。そして、その進捗を確認・支援し、年度末には達成状況をふり返る——このサイクルを繰り返すことで、キャリアパスが単なる“絵に描いた餅”ではなく、実際の成長と連動した仕組みになります。
上司側も、支援役・伴走者として部下と向き合うことで、育成力が高まり、職場全体に前向きな風土が根づいていきます。
4.キャリアパスに沿った成長機会の提供を
キャリアパスを機能させるためには、それに沿って段階的な成長のための機会を提供することが欠かせません。特に中小企業においては、日々の業務のなかで、上司が部下の成長を見据えた仕事の割り振りを行うことが、非常に重要です。
その際に大切なのは、「今この人ができること」だけで業務を割り当てるのではなく、「次のステップに進むために必要な経験」を意識して仕事を計画的に任せるという視点です。
たとえば、「この工程はまだ任せるには不安だけど、上司がフォローできるタイミングで少しずつチャレンジしてもらおう」「来年には後輩指導を担ってもらいたいから、今のうちにペアで新人と動いてもらおう」といった配慮が、自然な成長機会につながります。
また、特別な研修を用意しなくても、業務のふり返りや先輩との会話、上司との1on1ミーティングなどを通じて、気づきや学びの機会を日常の中でつくることができます。こうした工夫が、社員の成長を後押しします。
まとめ
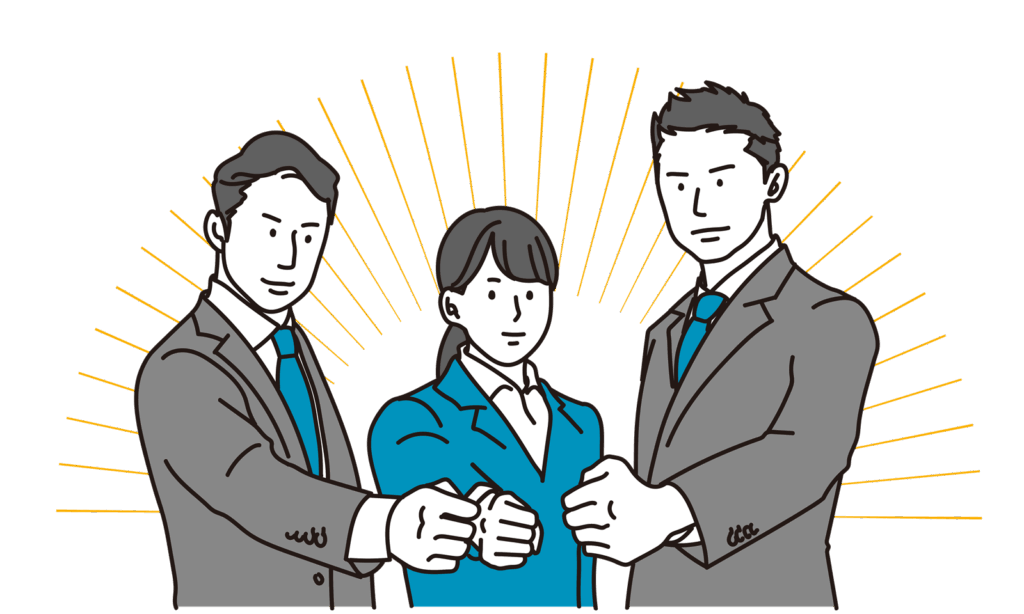
社員一人ひとりが「この会社で成長していける」「自分の未来が描ける」と感じられる環境づくりは、定着に直結します。そのためには、キャリアパスという“未来の地図”を示し、それに沿って機会を与え、支えていく姿勢が欠かせません。
「この会社で働いていて良かった」と思える職場は、経営者が社員の成長を心から願い、それを支援しようとする姿勢があるからこそ生まれます。中小企業だからこそ、一人ひとりに目が届きやすく、丁寧なキャリア支援ができるはずです。
社員の可能性を信じ、成長を後押しすることが、結果として定着につながっていくのです。
プロフィール
社労士事務所CRAFT 代表
採用定着士/特定社会保険労務士 高木 厚博(たかぎ あつひろ)
1974年大阪生まれ。私立清風高校、関西大学法学部卒業。大手外食企業にて、店舗管理等を経験。
退職後バイトをしながら試験勉強をし、社会保険労務士試験合格。地域最大級の社労士事務所に勤務。約15年勤務したのち2019年11月独立開業。顧問先企業の人事・労務の課題解決に取り組む一方、「採用と定着で中小企業の発展を支援する」をミッションに、採用支援、賃金制度・評価制度構築、「パワハラ予防研修」や「承認力向上研修」などの社内研修で中小企業の社員の定着・育成を支援している。
金融機関、商工会議所主催セミナーなど講演実績多数。パワハラ予防士。承認ファシリテーター。
著書「うちはいい会社です!と社員から言われる就業規則25のチェックポイント」(共著、泉文堂)。
NHK総合テレビ「おはよう日本」『103万の壁 企業の足かせ』出演。
好きな飲み物:よなよなエール 好きな食べ物:天下一品こってり
【連絡先】
〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮1-26-7 ラミアール聖蹟508


