<第6回> “相談できる先輩”が支える!定着を後押しするメンター制度のつくり方
TAMA WORKをご覧の皆さん、こんにちは。採用定着士/社会保険労務士の高木です。
「採用と定着で中小企業の発展を支援する」をミッションとして、多摩地域を中心とした中小企業のサポートをさせていただいております。
この記事では「せっかく採用したのに…を防ぐ!社員が定着する職場づくりのポイント」と題して、
「採用はできたが、すぐ辞めてしまう・・・」
「定着率を上げたいが、どうしたらよいかわからない・・・」
といった人材定着にお悩みを持つ中小企業経営者、人事担当者、管理職の皆さんに役立つ内容を連載でお届けしています。
第6回の今回は「“相談できる先輩”が支える!定着を後押しするメンター制度のつくり方」についてお伝えします。
はじめに

中途採用者が職場に早く馴染み、定着するためには、安心して相談できる存在が必要です。上司には聞きにくいこと、同僚には気を遣って話せないことが、入社初期にはたくさんあります。
そんな中で効果的なのが「メンター制度」です。先輩社員が“身近な相談役”として新入社員を支えるこの制度は、孤立や不安の軽減に大きな力を発揮します。今回は、中小企業でも導入しやすいメンター制度のつくり方と、成功のポイントを詳しくお伝えします。
1.メンター制度とは?

メンター制度とは、先輩社員が新入社員(中途採用者含む)を一定期間サポートする制度です。職場のルールや業務の進め方だけでなく、ちょっとした悩みや人間関係など、気軽に相談できる関係性を築くことが目的です。
メンター制度の基本構成:
・メンター(指導する先輩社員)
・メンティー(新しく入社した社員)
・期間の目安:入社後3カ月〜6カ月程度
ポイントは、上司ではなく“近い立場の先輩”が担当すること。心理的なハードルが下がり、素直に悩みを打ち明けやすくなります。
2.メンター制度が定着に効果的な理由
❶“相談相手がいる”という安心感
職場に「何かあったらこの人に相談すれば大丈夫」という存在がいるだけで、精神的な安心感が大きく変わります。これは特に、最初の数カ月に大きな影響を与えます。
❷組織のルールや暗黙知の習得が早まる
業務マニュアルには載っていないような「この書類は誰に回すの?」「この資料はどこに保存しておけばいいの?」といった職場の“当たり前”を自然に学べることも、メンターの役割です。
❸承認と自己効力感の向上
メンターから「よくやってるよ」「そこは私も最初苦労した」と言われることで、新人は「自分もやっていけるかも」と感じられます。この“承認”は定着の大きな推進力になります。
3.導入のステップ
効果的な1on1ミーティングを行うためには、流れを押さえておくことが大切です。以下は具体的な流れの一例です。
❶メンターの選定
・できれば同じ職種、部署、世代が近い社員が理想
・指導力よりも「人当たりの良さ」「親しみやすさ」を重視して選定
❷メンターへの事前説明・研修
・メンター制度の目的をしっかり共有
・「業務の指導ではなく、寄り添い・相談相手であること」を強調
・傾聴や承認のコツを短時間でもレクチャー
❸運用ルールの設定
・期間(例:3カ月)
・週1回の面談(15〜30分)
・終了時の振り返りアンケートの実施 など
4.面談の内容と進め方
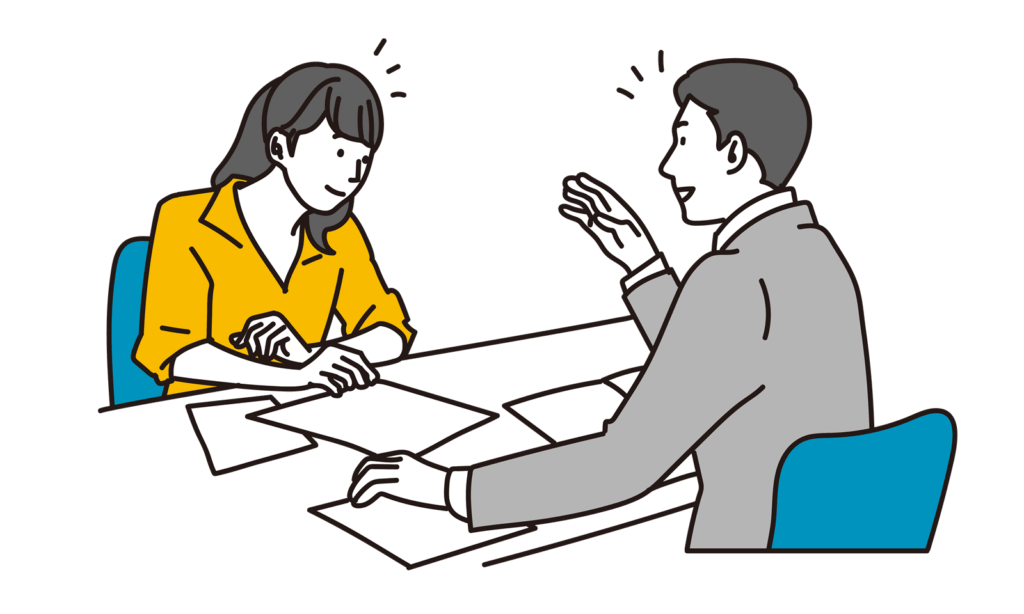
メンター面談は、単なる雑談に終始するのではなく、ある程度の流れや目的意識を持って進めることが望まれます。
【面談の基本的な流れ】はこちらになります。
❶アイスブレイク(5分程度)
雑談や共通の話題で緊張をほぐす。休日の過ごし方や趣味の話など、業務に関係ない内容も歓迎です。
❷近況の確認(5〜10分)
業務の進捗や困っていること、気になっていることについてざっくばらんに話を聞きます。ここでは否定せずにしっかり傾聴する姿勢が大切です。
❸承認と励まし(5分程度)
小さなことでも「頑張ってますね」「それは助かります」と伝えることで、自己効力感を育みます。
❹アドバイス・共有(5〜10分)
新人が戸惑っていることに対し、自分の経験や工夫を押しつけにならない形で共有します。「私はこんなふうにしてたよ」といった形が有効です。
❺まとめ・次回の確認(数分)
次回の面談日程を確認し、今日の会話を簡単に振り返ります。
このように、短時間でもしっかりと目的を持って話すことで、関係性の深まりと成長の後押しが可能になります。
5.成功のポイントと注意点
❶メンター任せにしない
人事担当者や上司が定期的にメンターと連携し、必要に応じてフォローを行うことで、制度が形骸化せずに運用できます。
❷メンターを“評価”しない
「メンターが評価される」となると、メンタリングが義務的・形式的になってしまう可能性があります。あくまで信頼関係を築く“サポート役”としての役割に留めましょう。
❸中途採用者の声を制度に反映
運用中や終了後に、メンティーからのフィードバックを得て、制度の改善に活かすことが大切です。
6.導入事例
ある製造業の会社では、20代〜30代の中途採用者の早期離職が続いていたため、2年前からメンター制度を試験的に導入。先輩社員と週1回のミーティングを実施したところ、「職場の雰囲気がわかって安心した」「相談できる人がいるのは心強い」との声が多く寄せられ、半年後の定着率が20ポイント改善。現在では、すべての中途入社者に対して実施されています。
まとめ
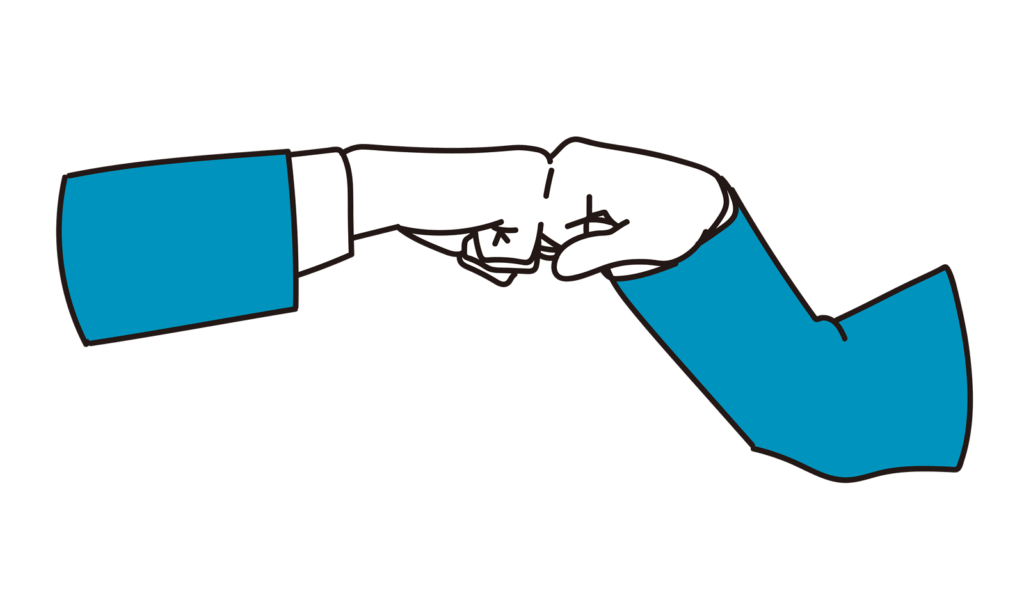
中途採用者が職場に早く馴染み、安心して働き続けるためには「誰に相談できるか」が大きなポイントです。上司や同僚とは異なる立場の“相談できる先輩”として、メンター制度は有効な支援策となります。
大がかりな仕組みを整える必要はありません。まずは「先輩社員に週1回15分、話を聞いてもらう」そんな小さなスタートでも十分効果があります。
中途採用者の不安を和らげ、職場に馴染むスピードを高めるためにも、自社に合った形でメンター制度を導入してみてはいかがでしょうか?
プロフィール
社労士事務所CRAFT 代表
採用定着士/特定社会保険労務士 高木 厚博(たかぎ あつひろ)
1974年大阪生まれ。私立清風高校、関西大学法学部卒業。大手外食企業にて、店舗管理等を経験。
退職後バイトをしながら試験勉強をし、社会保険労務士試験合格。地域最大級の社労士事務所に勤務。約15年勤務したのち2019年11月独立開業。顧問先企業の人事・労務の課題解決に取り組む一方、「採用と定着で中小企業の発展を支援する」をミッションに、採用支援、賃金制度・評価制度構築、「パワハラ予防研修」や「承認力向上研修」などの社内研修で中小企業の社員の定着・育成を支援している。
金融機関、商工会議所主催セミナーなど講演実績多数。パワハラ予防士。承認ファシリテーター。
著書「うちはいい会社です!と社員から言われる就業規則25のチェックポイント」(共著、泉文堂)。
NHK総合テレビ「おはよう日本」『103万の壁 企業の足かせ』出演。
好きな飲み物:よなよなエール 好きな食べ物:天下一品こってり
【連絡先】
〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮1-26-7 ラミアール聖蹟508


