「梅澤朗広の採用SDGs」第13回目は、「中小企業でもできる!脱炭素経営の第一歩『見える化』から始めよう」です。




実は最近、脱炭素経営のことを社長さんとお話をしている時に、よく言われることがあります。「脱炭素経営って、カーボンニュートラルとか、GXとか、グリーントラスフォーメーションとか、スコープ1とか、これからの世の中に大事なことなんだろうとは思うんだけど、カタカナ用語ばかりで分かりづらいんだよね、、、」
本当に、言われることが多いのです。10人に話したら、9人くらいの割合です。製造業や建設業で規模の大きい企業だと、取組を始めている会社もありますが、私はこの脱炭素経営について、もっと多くの方に伝えたい。多摩地域の経営者の発展に貢献したい、、、 そこで、シンプルで分かりやすい言葉で、読みやすいように記事を書いてみようと、これまでの私のキャラクターをチェンジしてみようと思います!
目次 ➖
改めて「脱炭素」ってなに?…
最近よく耳にする「GX」や「カーボンニュートラル」という言葉。どれもかっこよく聞こえるけれど、正直ピンとこない…そんな方も多いのではないでしょうか?
「GX(グリーントランスフォーメーション)」というのは、ざっくり言いますと、“環境にやさしい経営に切り替えていこう!”という流れのことです。
つまり、環境にも、会社の未来にも、ちゃんと優しい経営をしていこうという話です。
しかし、具体的に何をすればいいのか、、、。

よくあるアドバイス:「とりあえず再エネ導入しましょう」
ご提案を受けたことがあるかもしれません。太陽光パネルを社屋の屋根にのせたり、電気自動車に切り替えたり。
しかし、少額ではない費用がかかるし、すぐにはできない、というのが多くの中小企業の本音でしょうか。
やる気はあっても、予算がない。メリットはあるの?
「何もしない」でいいわけではない
ここが悩ましいところです。しかし、脱炭素は、将来的には取引先との関係や補助金の獲得、果ては採用活動にまで影響してくるテーマです。取引先からCO2の排出量を算出してレポートを出すように言われた、補助金を申請する際に審査において加点要素となる、環境を大切にする教育を受けた世代が就職活動をしている、、、
つまり、「やらない理由」はたくさんあっても、「やらないでいい」理由は意外と少ないということです。
「見える化」で得られるメリット、けっこうあります
見える化って、やってみると結構面白いんです。
「え、こんなところでこんなに電気使ってたの?」とか、「みんな意外と無意識にムダ遣いしてるな…」とか、気づきがいっぱいあります。
たとえば、東京都多摩地域にある従業員20名ほどの町工場では、照明と空調の稼働時間をタイマーで管理するようにしたところ、年間約60万円の電気代削減につながったそうです。これは、高級な焼肉でのお食事60回分くらいのインパクトですね。
社員の節電意識も高まり、みんなで改善案を出し合うようになったとか。ちょっとしたことだけど、それが文化になるって素敵なことだと思いませんか?
さらに、実際に「見える化」に取り組んで成果を出している中小企業の事例もあります。
・株式会社大川印刷(神奈川県・印刷業)
年間電気料金 約190万円削減。
毎月の電気使用量をグラフで共有したことで、社員の節電意識も大幅にアップ。
・山形精密鋳造株式会社(山形県・鋳造業)
生産プロセスの見直しによる、電力・燃料費を大幅カット。
年間エネルギーコストを約900万円削減
こうした事例を見ると、「うちに取り組んでみたい」と思えてきませんか?
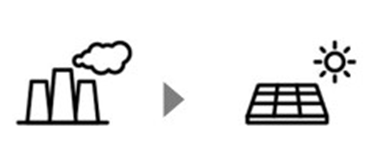
無料ツールや支援制度も活用しよう
多摩地区では、八王子商工会議所が会員企業向けに支援する制度「見えサポ」があります。
正式名称は「見える化サポート事業」。省エネやCO2削減などの課題を抱える企業に対して、専門家が現場を訪問し、アドバイスや改善提案をしてくれる取り組みです。
「設備を更新する予算はないけど、できることから始めたい」という企業にぴったりで、導入コストがかからない点も魅力。
実際の導入事例や申し込み方法など、詳しくはこちら(八王子商工会議所公式ページ)から確認できます。地域に根ざしたこうした支援策は、相談のハードルが低く、取り組みやすいのが特徴です。
実は、東京都や環境省では中小企業向けに無料で使えるツールや支援制度がいろいろ用意されています。
たとえば、
東京都の「省エネ診断サービス」では、専門家が会社に来てくれて、どこにムダがあるか教えてくれます。 実際に多摩地域の精密部品加工会社ではこの診断を受けた結果、昼夜で空調の使い方に大きなムラがあったことが判明し、運用改善だけで年間約40万円の光熱費を削減できたという例もあります。
「エコアクション21」は、CO2の排出量などを記録・管理しながら、継続的に改善する仕組み。環境経営の初心者にもわかりやすいです。
環境省の「見える化ツール」は、業種別にCO2排出量をざっくり計算してくれる優れモノです。
こういった制度は、「使わなきゃもったいない」と思えるくらい便利です。
見える化は中小企業にとって実践可能な第一歩
「脱炭素」と聞くと、遠い未来の話に感じがちですが、見える化なら今日からでも始められます。
そして、これは単なる環境対策ではなく、コスト削減、社員の意識改革、ひいては採用や取引の強化にもつながっていく話です。
派手さはなくても、「地味だけど、いいことがたくさんある」取り組み。それが見える化です。
実際、東京都の八王子市のある製造業の社長さんは、「数字で電気のムダが見えるようになったら、社員たちの反応がまったく変わった」と話していました。誰かが上から言うより、自分たちで気づいて動けることのほうが、ずっと効果があるのだそうです。
こうした気づきが、小さな工夫や省エネアクションにつながり、やがて大きな成果になっていく。そう考えると、見える化って、ちょっとした経営のスイッチになるのかもしれません。
何より、こういう一歩って、ちょっと誇らしい気持ちになれるんですよね。
ぜひ、できるところから、はじめてみませんか?
プロフィール
梅澤 朗広
SDGusサポーターズ株式会社 代表取締役
日本JC公認SDGsアンバサダー
FC NossA八王子 アドバイザリーボード
大切にしている価値観:感謝・貢献・共創
野村證券、東京ヴェルディを経て2019年にSDGusサポーターズ株式会社を設立。SDGsの「持続可能な社会の実現」「誰一人とりのこさない」の理念に共感し、企業に対してCSV(共通価値の創造)の観点で事業活動と社会活動の両立に向けた経営サポートをおこなっています。SDGsと自社の活動に対する理解を深めてアクションを考えるワークショップや、様々なパートナーと連携して営業・広報・採用のサポートをおこなっています。
SDGsについて興味を持っている・相談したいなど、ぜひコチラにお気軽にお問合せください。


